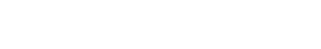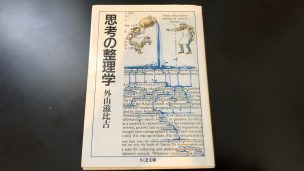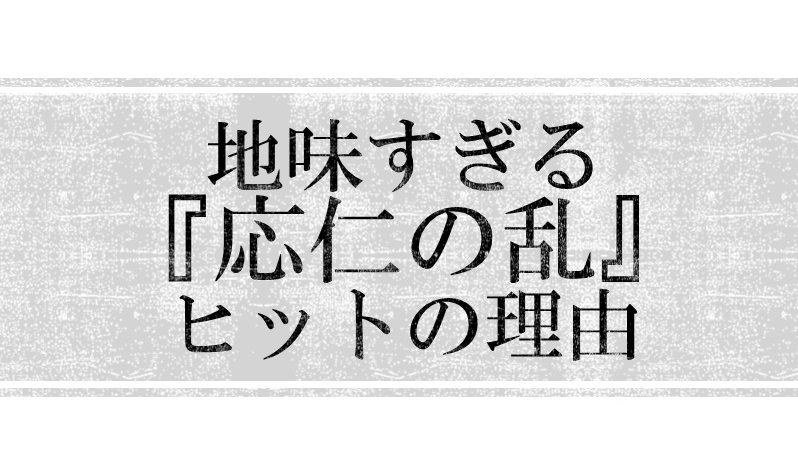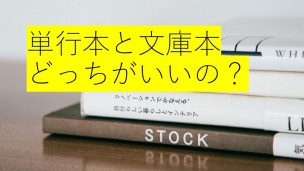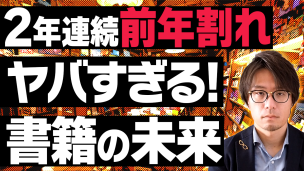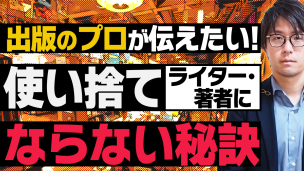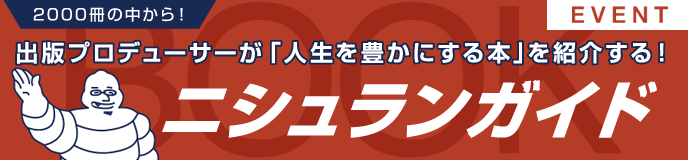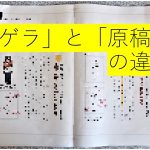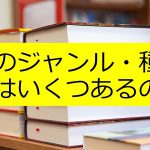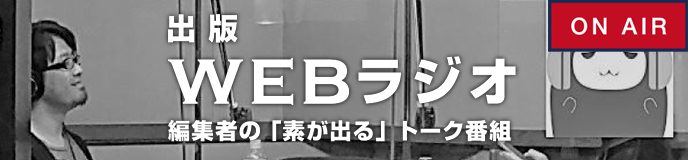昨日、「日本語を『正しさ』を重視して伝えていくのは難しい」という話を書きました。
↓
言葉は多義語と呼べるくらい多面的なものもあって、「正しい」使い方を厳密に考えると使い方が限定されていくが、多面的に見ていくとどんどん「使い方」が増えていくからです。
ということはコメンテーターの「人間性の合う合わないってありますからねぇ」も結局は正しい使い方と言えたわけです。
目次
「敷居が高い」のは誰のせい?
また、他の例として「敷居が高い」という言葉もあります。
これは「あそこは一番安いコースで2万円の高級店だから」「あの店は由緒ある料亭で自分にはちょっと・・・」と、「高級すぎる」「上品すぎる」ので行きにくいお店、といった意味で使いますよね。
でもこれも本来の意味ではないのだそうです。
敷居が高いとは「ツケがたまっている」とか「酔って相手に絡んで怒られた」など「自分が何か悪いことをした、不義理をしたので顔を出しにくい」という意味で使われる言葉だそうです。(ちなみに店に限らず、友人の家に対してでも使える)
僕も恥ずかしながら数年前に『文化庁国語課の勘違いしやすい日本語 』を読むまで知らずに誤用していました。
そこで使いかたを改めようかなと思ったのですが、本書には年代ごとに言葉の意味をどう認識しているかに関するアンケート結果も掲載されており、それを見るに「50代以上は50%以上の方が正しい意味で使っていて、30%以上の方が『高級すぎる』『上品すぎる』の意で使っている」「40代では47.4%が正しく、35.6%が誤用」「30代以下20代、10代では20%以下が正しく、70%以上が誤用」であることが分かります。
これを見て「そういうことか」と思ったのです。言葉を正しく使えていないのは、別に10代20代の若者に限ったことではないのです。いい大人の僕らも間違えているし、50代以上でも30%以上の方は誤用しているのです。
もちろん、若い方とご年配の方であれば、年配の方が正解率は高い傾向にあります。でも、50代でも「敷居が高い」を3割以上が間違えていることを知って「若者が言葉を知らないのではなく、今の年長者も、たとえば80代の方に比べたら言葉を知らないし、80代の方々も、大正1ケタ生まれ、明治後期生まれの方々に比べれば正しくない日本語を使っているんだろう」と思ったのです。
正しい日本語とは
言葉の正しい意味を探り始めると「正しさ」という多様性の前に「正しい意味って何だ?」と思うし、「正しい日本語」も時代と共に変遷してきて、「それ、何時代の正しい日本語のこと聞いてる?」と確認しないと成立しません。でも時代で変わる「正しさ」って、絶対的な正しさとは言えないですよね、本当はもっと柔軟で弾力性のあるものかもしれません。
今回僕が言いたかったのは、あくまで「言葉の正しさ」「正しい日本語」に囚われすぎるのは、ひょっとしたら自己矛盾を抱えることになるかもね、ということです。
その言葉を使う背景や、時代や年代など、TPOごとに「正しさ」が変わってしまうから、むしろ「絶対的な正しい日本語」を定義できないのです。今、この場での正しい日本語はあるけれど、100年前の日本人からすれば「いや、君たち間違ってるよ?」と言われかねません。
でも勘違いしてほしくないのは、僕は「言葉を知ろうすること」そのものは肯定派だということ。
言葉を学んだり、その意味や由来を調べることはその人の教養となり、内面の世界を魅力的なものにしていきます。「語彙力」は多い方が良いと思うし、似たような言葉の意味の微妙な違いを知ることは、いろんな物事を多面的に、繊細に受け止めたり表現できるようになるきっかけだと思います。「人間性」という言葉の多面性を知ることもその一つですね。
北は「その人らしい言葉で話す人」に魅力を感じるので、他人の言葉をそのまま借りないで済むよう、いろんな言葉を吸収して、自分らしく使える人がもっと増えて欲しいと思います。僕自身も含めてですけど。
ただ「これが正しい」と決めつけすぎるより「かつてはこんな意味で使われていたが、現在では7割の人が別の意味で使ってる言葉」として柔軟にとらえてもいいのかなと思います。
僕は今のところ、そうすることでバランスを取ることにしました。そうしたら、今生きている言葉をどんどん知りたくなって楽しいですよ。
今は「わかりみ」「やさしみ」などの「み」っていう言葉を使いこなしたいと思っています(笑)