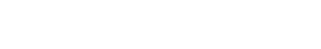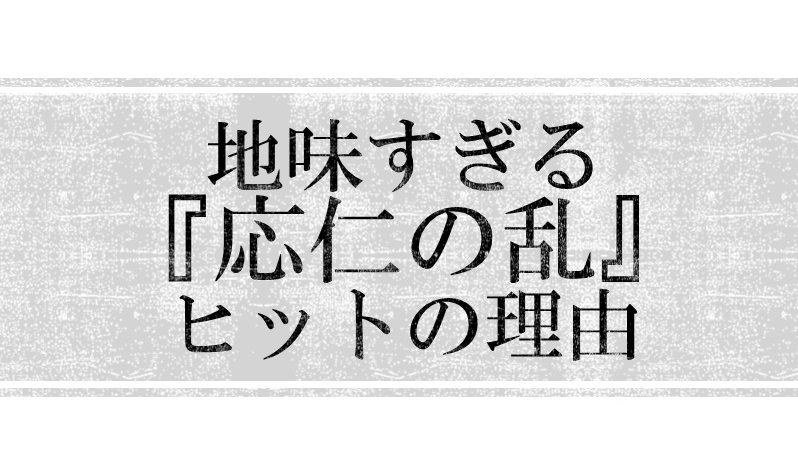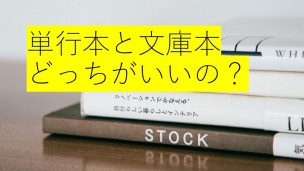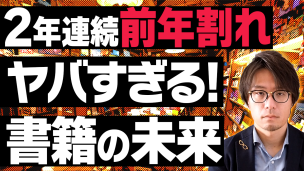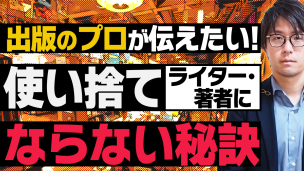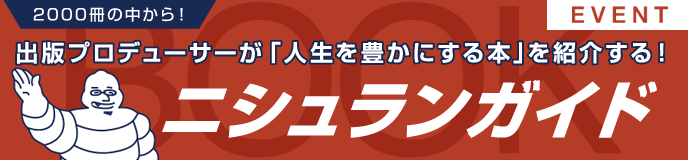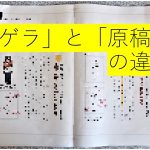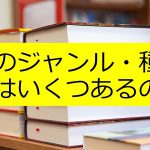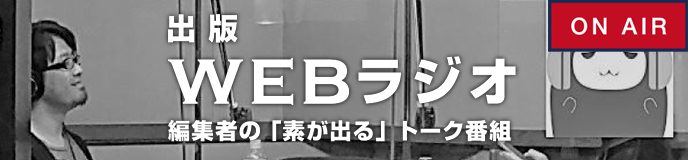先日、著者と販促の話をしていて「そもそもなんで記事書いてサイトを更新していくんでしたっけ?」と聞かれました。
そういう「そもそも論、大歓迎」ですね。
もちろん過去にも説明はしていますが、人間は「一度言われた」くらいでは何も覚えていません。正確には「覚えているが、心の底から深く刻み込まれたわけではない」のです。
「ふーん、なるほど」と理解&記憶したに過ぎません。これでは本当の意味で身についたことにならないです。
むしろ「あらためて、これってなんでやってるんだっけ?」と自分で疑問に思ったり、困ったりしたときにこそ、自分の行動や習慣すらも変えるくらい深く刻み込まれるのだと思います。
だから大事なことこそ、何度でも説明します。
目次
著者として誰も追いつけないところまで行く
さて、なぜ著者メディアを作って、記事を更新するのか?
それは究極的には「あなたが、著者として誰も追いつけないところまで行くため」です。
著者メディアはあなたと読者を結ぶ場として運営します。
あなたのことを知っている人や、あなたの本を読んだ人であれば名前や書名で検索するのでたどり着くことは簡単です。
しかし大切なのは「あなたのことを全く知らない方」に、あなたを見つけてもらうことですね。
この人「面白そう」、この人の「セミナーに参加してみたい」「本を読んでみたい」と思ってもらえる場がないと、著者として長く活躍できません。
本屋さんに来てくださった方の目に留まるようにするのは、本のデザインだったり、オビのキャッチコピーだったり、良い場所で置いてもらえるよう交渉する出版社の営業さんの仕事ですが、そもそも本屋さんに読者の足を向けてもらうのは著者の仕事です。(広告もそうですけどね)
そのためにはあなたのことを知らない人が、あなたの本やセミナーに興味を持ってくれる情報発信が必要ですね。
それには、想定読者が検索しそうなキーワードで、あなたのメディアが「1位表示」されるのが最も強いです。広告費も不要ですし。
いわゆるSEO(サーチエンジン最適化)というやつです。
検索で1位表示される記事の資産価値
例えば、この出版TIMESでは「本を出版してベストセラーにしたい」という方をメイン読者と想定して記事を作ってます。
本を出せたらいいなぁとか、ブランディングのために本を出す!という「なんとなく」や「自分満足」ではなく「ベストセラーにする!」という熱い志の人です。
そういう方は「本気度」も高いので「お金」「出版の費用」について知りたいだろうな、本気だからこそそういう情報が欲しいだろうな、と考え出版費用に関する記事を作成してあります。
↓
この記事は2017年の8月29日に書かれていますが、11ヶ月経った2018年7月現在でも「本 出版 費用」「本 費用」「出版 費用」といったキーワードで平均して「1位~1.2位」を維持し続けています。(なお現時点では一切、出版TIMESは広告を出していません。)
「書いておわり」ではなく、ちゃんとSEOを意識して記事を書けると、このようにずっと読者様を連れて来てくれる「資産価値の高い記事」になります。
すると、僕が情報を届けたいと願っている【「ベストセラーにする!」という熱い志を持った人】が、「出版費用」と検索するたびに、出版TIMESを訪問する確率が高いのです。
他にも「出版プロデューサー」で1位、「商業出版」で1位、「本を書く」で2.1位、「本 印税」で3位など、ある程度狙って上位化できるようになってきました。
「出版プロデューサーって何なんだっけ?」「商業出版するには」「本を書くには」「本の印税っていくらなんだろう」と疑問に思っている方に高確率で僕や出版TIMESのことを知ってもらえます。
ちなみに自費出版は原則として弊社の守備範囲外(よっぽど面白いものだけやらせてもらってます)なので、不要っちゃ不要なのですが、先ほど紹介した
の記事は「自費出版 いくら」で3.8位、「自費出版 費用」でも14位に入っています。
14位は大したことじゃないですけど、3.8位はそこそこボリュームもあります。
「評価の高いページ」は「関連するキーワードでも評価されやすい」傾向にあります。
他の記事や、別のクライアントさんのサイトでも同様の現象は見られます。
さらに「特定ジャンルのキーワードで評価の高いページを複数持つサイト」は全体的な掲載順位が上がっていきます。
出版TIMESでは「出版系」キーワードで記事が上位化されるごとに、他の記事の掲載順位も上がっていったのです。
コツコツという圧倒的武器
サイトの評価基準は複数あります。
専門性・権威性・信頼性(E-A-T)や、指名検索の多さ、プレゼンス(存在感)。
※指名検索は「出版TIMES」と直接検索するような「このサイトが見たい」という指名の検索
評価基準が複雑で高度になってきた結果、小手先のテクニックでは上位化されなくなってきました。
一度上位化された記事でも、油断していると下落することもあります。
これは逆に言えば、自分が
- 「専門的で信頼性のある記事」を書き
- それをSNS上でも検索上でも認知され、
- 指名検索されるようになってきて、
- 「権威性」を獲得したら
もう、だれにも追いつかれることはないということです。
僕は自分がプロデュースする著者は「そのジャンルにおいて日本一だ!」と思ってやっているので、web上でも「誰にも追いつけない圧倒的1位」であって欲しいと思っています。
だからSEOを意識して記事を書きつつ、記事数を増やしてくれるよう言い続けるのです。
Googleのアルゴリズムは複雑ですべてを解明できるわけではありません。
僕らサイト運営者は、結局のところ想定読者にとって有益な情報を発信し続けて、評価されるサイトにしていくしかありません。
それが結局のところSEOになるのです。
- ちゃんとしたやり方(SEOやメディアの運営法)で
- 誰でもできることを(記事を書く)
- 誰にもできなくらいやる(コツコツまじめに)
これが誰にも追いつけないところまで行くための、一番の近道なのではないでしょうか。
凡事徹底。
本気の著者にぴったりの言葉です。