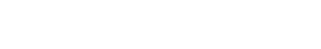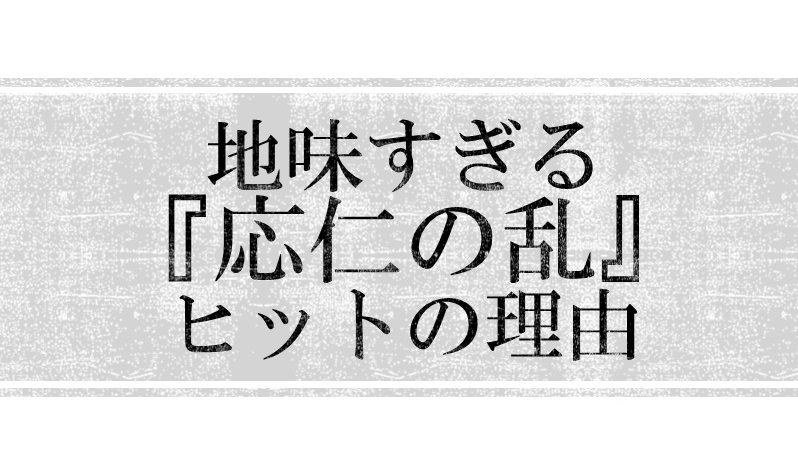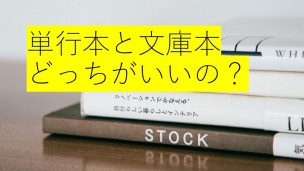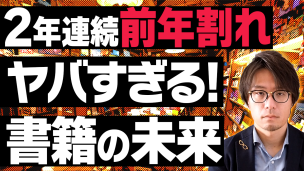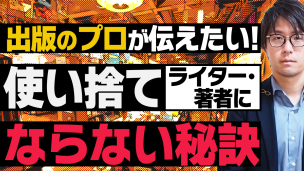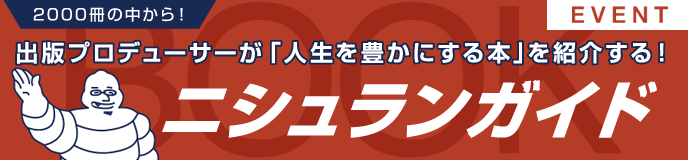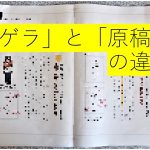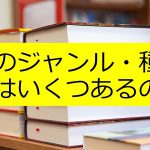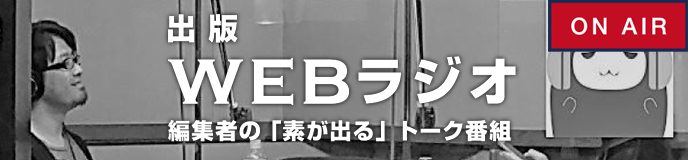土日の朝はパン派の出版プロデューサー西浦です。
毎日更新61日目。
こちらの記事を書いたところ大変反響をいただいたので、今後も継続して「出版業界の解説」をお伝えしていこうと思っております。
さて何からやるべきかと言うと、やはり「用語解説」からかなと思うのですが、wikiに載ってあることを書いてもしようがないので、wikiに書いてあることの裏を読み解いたり、そもそも辞書にすら載ってないだろうということを中心にお届けいたします。
最初はこの言葉から、、、
目次
何をどこに置くかは書店さんが決めることなんで
「何をどこに置くかは書店さんが決めることなんで」とは…
著者が意図する本屋さんや、良い場所で、本を並べてもらえないことについて、編集者や営業担当者に質問した(文句を言った)時に返ってくる言葉の一つ。
つまりは「その店やその売り場に置かれてないのはしょうがないでしょう。こっちのせいじゃない。」っていう意味。編集者が営業に言ってこの言葉を返されるパターンもある。
背景
本の販促において「どの書店の、どの売り場に、どのように置かれるか」は最も重要な要素であり、著者はもちろん、編集者も営業も強く気になるポイントの一つとなっている。
大型店、有名店の「話題書」コーナーに置いてほしいという要望は当然強く、そうでなくとも本の特性や読者属性ごとに「合う」書店さんがあるので、やはり相性の良い店での展開は販促上の観点からも必須といえるだろう。それ以外に著者の地元や会社の周囲においてほしいという要望を受けることも多い。
こういった「どこに置くか」の議論が生まれるのは「売れているとき」と「売れてないとき」の2パターンある。当然、前者の場合は「何をどこに置くかは書店さんが決めることなんで」とは返されにくい。売れている本は書店さんも反応が良いし、営業もいろんな可能性を前向きに検討しているからである。
よってこの言葉は「売れてない」か「発売直後でまだ実績不足」という背景から生まれやすい。
概要
そもそもこの言葉の字面通りの意味「どこに何を置くかは書店さんが決めること」というのは真実である。そこにウソはない。しかし裏の意味が存在する。つまり「販促について口を出すな」という釘差しの意味だ。
そもそも書店営業というのが「どこに自社の本を何冊置いてもらうか提案する仕事」であり、書店さんと自社の双方の売上が最大化・最適化するよう、常に働きかけていくものだ。
よって「書店さんが決めることだから」という返事については、本来「そんなことは分かってる」「その前提で提案して実現していくのが営業の仕事だろう」というリアクションが正しい。
元・営業の自分が言うのだから間違いない。
でもこの言葉が発せられることは多いし、自分も営業時代何度か(何度も?)使用した。
それは言葉通りの意味が真実であるために「これ以上販促に口を出すな」という印籠のような効果があるからである。
この返答をされて「いや、それを提案していくのが営業の仕事だろうが!」と言える編集者や著者は強すぎる。よほどの実力者か、変人(悪い方の意味)しか無理だろう。言った後はほぼ間違いなく営業との関係が悪化するので使用はおすすめしない。
真の意味 と 対応
背景の項目でも説明したが、「どこに置くか」の議論が生まれるのは「売れているとき」と「売れてないとき」の2パターンある。正確には「売るのに積極的なとき」と「売るのに消極的なとき」と言った方が良いかもしれない。
まず「売るのに消極的なとき」というのはどういったケースだろうか?それは発売後の売れ行きが悪いときだ。
すべての本に均等に販売力を配分するのは、経営判断として下策だ。本は増刷を繰り返す方が利益率が上がるし、タイトルを絞って部数を伸ばした方が「売れていること」が呼び水となってさらに売れやすい。よってお金や人員をかける本を取捨選択する必要がある。
そしてほとんどの本は取捨の「捨」を選択される。売れ行きの悪い本の方が多いからだ。だいたい発売1週間、遅くとも2週間で明暗が分かれている。
だから発売2週間以上経っていて売れ行きが芳しくない場合、その本のことだけを考えたら「売り場を変えよう」「もっと大きく展開して目立たせよう」という提案は理に適っているが、会社全体で考えた時は非合理的と判断される。現時点で売れてないものが、今後売れるかはバクチだが、限定的にでも現在売れているものの方が今後売れる確率は高く、書店さんにも提案しやすいからだ。
この場合に営業から、著者や編集に発せられる「どこに何を置くかは書店さんが決めること」という言葉は「その本は売れ見込みがないので、放置する」というのとほぼ同義であり「黙れ」と言われたのと同じである。最後通告だ。でも、出版はビジネスの世界でありシビアな陣取り合戦なので、この状況では著者や編集者側から文句を言うのはお門違いとなる。
厳しいようだが「売ってほしかったら売れる本を作って来い」という現実がある。
もう一つのケース、つまり対象の本が売れているときや、発売前&直後の「期待値が高いとき」には営業も会社として「売るのに積極的」である。
この時は営業もちゃんと提案の仕事をしてくれるので「A書店では女性エッセイのところで売れているよ」「レジ横にラックで仕掛けたら飛ぶように売れた!」「〇〇との併売が多いから提案材料に使えるかもしれない」と情報共有やデータ分析を経て、みんなで「担当の書店様から適切なお店を選んでご提案しに行こう」となる。
この時に営業内で「どこに何を置くかは書店さんが決めることでしょう?」とか言う営業がいたらたぶんめっちゃ怒られるし、バカにされる。「お前、仕事やる気ないのか!?」となるだろう。
この提案を経ても、書店さん側が、思うように反応してくれないときはある。「提案はしたけど、のってもらえなかった」ということだ。
これは営業として仕事自体はしている。書店さん側が判断を間違ったのかもしれないし、営業側の提案方法が間違っていたのかもしれない。提案する相手(お店)選びを間違ったのかもしれないし、そもそも提案内容が間違っていたのかもしれない。
売れると思って提案しているわけだから、その提案に乗ってもらえないのはスタートラインに立てていないわけで、営業として技術やスキルを磨いていかないといけないだろう。しかしそれは次の段階の話で、今後の課題になる。
この場合に営業や編集から「書店さん側が決めることなんで」と言われたら、正しくは「うん、僕らもそう思ったから提案したけどダメだったよ。でもどこに何を置くかは書店さんが決めることだから」と言う意味だ。「なのでこれ以上は言ってくれるな」というニュアンスになる。
この場合は本が売れているのだから「セミナーではこういう参加者が多い」「著者メディアには〇〇というキーワードで検索してくる人が最近すごく多い」など情報共有をどんどんしたり、別パターンを提案することは喜ばれるだろう。それが実現できるかは営業次第でもあるが、それが強い営業、弱い営業の差だったりする。
むろん、前者の意味で使われることの方が多い。
類義語
よく似た返答に「すべての本を同じようには並べられない」「あなたの本ばかり売るわけにもいかない」などがあり、これらに比べれば「何をどこに置くかは書店さんが決めることなんで」の方が営業側の優しさ配慮が含まれていると言えるだろう。