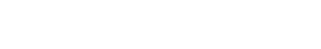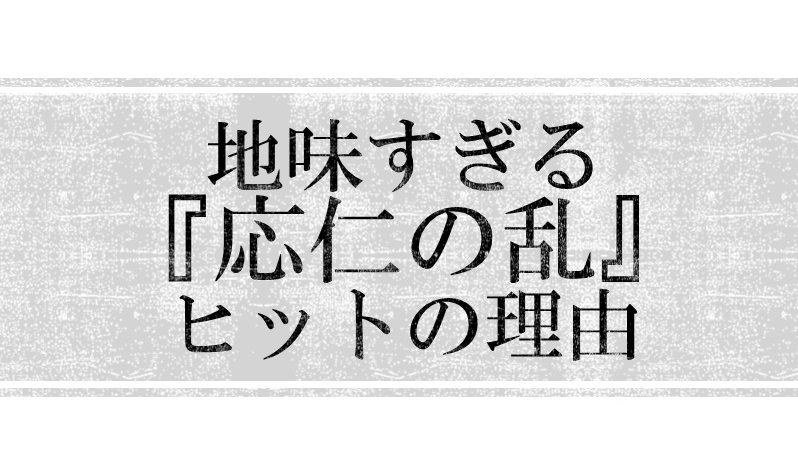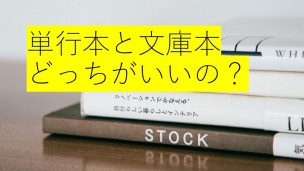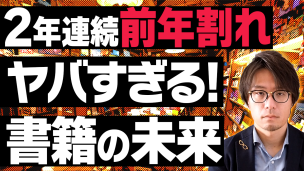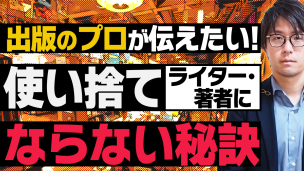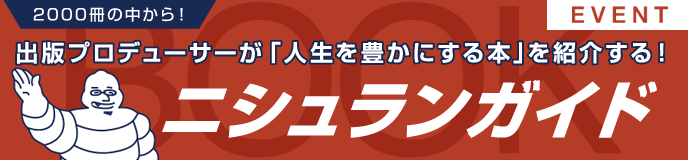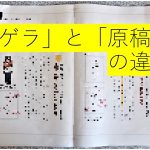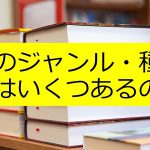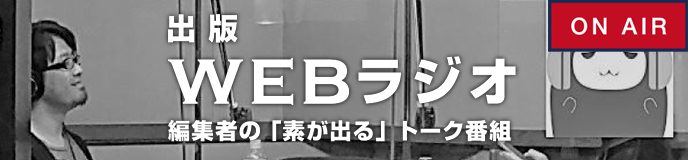「Hi-STANDARD」をはじめ多くのパンクロックバンドをプロデュースしてきた、音楽プロデューサー「ギース」さんとの対談記事その2。
※その3は「才能あるバンドと著者」の見つけ方
プロデューススタイルの日本と海外の違いとは何か?
バンドとのトラブルは何が原因なのか?
話はどんどん熱くなります。
お酒もまだまだ飲みます。
※焼酎(お湯割り)飲んでるので完全にガッツリモードです。
目次
プロデューススタイルの違い
西浦:プロデュースのスタイルで言うと、出版と音楽ってちょっと違いますよね。
日本の出版プロデュースは作品ごとっていうのが主流じゃないかな・・・
音楽みたいに「バンドそのもの」「著者そのもの」っていう「人単位」でプロデュースしてるのは、アップルシードさんとかくらいじゃないかと・・・
ギース:にいやんみたいな、作品ごとのプロデュースは音楽業界にもあるんだけど、海外に多いんじゃないかな。
500万とかでミュージシャンと契約して、そこにCD1枚のインセンティブをいくらプラスみたいな形の。
日本だとミュージシャンそのものを長くプロデュースしていく、アーティスト寄り(作品よりも)のプロデューサーが多いかな。
西浦:なるほど。「人単位」のアーティストよりのプロデュースだと何がカギになってくるんですか?
ギース:アーティストに頼られることかな?「この人いないと死んじゃう」と思われる、心理学的な力?
すぐ死にたがるからさ、ミュージシャンって(笑)
西浦:死にたがる!それは、なんかわかる気がしますけど(笑)
出版だと「書けない」とか「時間ない」とかはたくさんあるけど、死ぬはなかなか聞かないですね。
コミュニケーションと信頼
ギース:マイケル・ジャクソンも最後はカウンセラーに頼ったわけで。音楽やってる人はそういうとこあるよね。
「Metallica」の「Some Kind Of Monster」っていうドキュメンタリー映画で、
カウンセラーがバンドのカウンセリングしながら、マネタイズしていったの観てさ。
「なんだ、これプロデューサーができりゃいいんじゃん」って思って、
心理学とか勉強し始めたの、それがきっかけなんだよね。
西浦:そうだったんですね。ギースさんと初めて会ったのって、心理学のセミナーだったんで
「見た目のわりにマジメな人だな」と思ってました(笑)
ギース:いや、使えるんだよ?けっこう(笑)
バンドとのトラブルってたいていコミュニケーションのズレだから。
なんでか知んないけど、毎回バンドと殴り合いになるやつもいてさ(笑)
そういうやつに、昔は「気合がたんねぇ!」とか言ってたけど、
これじゃいつまでたってもダメだなってことで、言語化したくて心理学を勉強したわけ。
結局ラポール(信頼)なんだよね。
同じこと言われてもムカつくか、そうでないかは「信頼」があるかどうかだから。
にいやんはもう忘れてるだろうからさ、もっかいやりなおしたら?(笑)
西浦:うーん、そう言われると心理学ちゃんとやった方がいい気がしてきました。
本当にやり直そうかなぁ。
ギース:ラポールって実際にできてるかわかんないし、教わった方もすぐ飽きちゃうけど、一番大事だよ。
日本と海外でプロデューススタイルが違うとは・・・知りませんでした。
作品単位だと「売れるかどうか」がかなり重要な視点になるし、人単位だと「信頼できるか」がやはり重要な視点になりますね。
作品単位で売れなかったら目も当てられないし、人単位だと長く続けることで「縛られてる感」とか「慣れ」も出て来るかもしれない。
(もちろんプロデュースのスタイルに関係なく信頼・売れることは大事なのですが、あくまで比重の話)
ラポール(信頼)ってギースさんもおっしゃってるように、実際にはできているのかどうか見えないけど一番大事ですね。
プロデューサーとしてはもちろん、人として大事なのだと思います。
人と人とのことだからなぁ・・・やっぱりもう一回心理学セミナー学びなおそうかな。
次回はこの対談の最終回。
「プロデューサーの宿命」と「売れるバンド・著者の見分け方」です。
この話は人と向き合う、あらゆる仕事の人に読んで欲しいです。
おまけ
はい、ロッキンオー・・・ん?
おかしいな、モノクロにしたのにロッキンオンじゃないな。
これはギースさんの熱さが際立って良い写真なのに、僕のお湯割りがその空気を完全にぶち壊してる。
ちょっとバカにしてるくらいに見える(苦笑)
「ふんふん、なるへそ、へーそうなんだ、あ!お湯割りオカワリください!」という声が聞こえてくる。
(実際には言ってないですよ)
「おいー、聞けよー!」って言われそう。
(実際には言われてないですよ)
ラポールできすぎて、ダメな慣れが生まれている好例ですね。