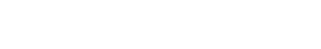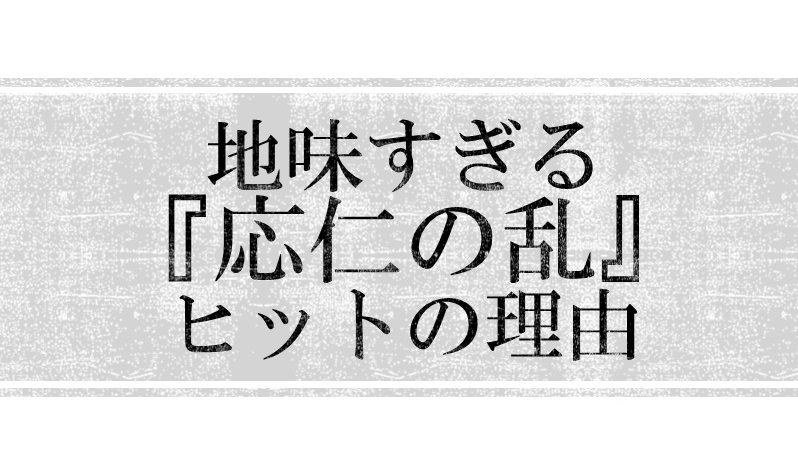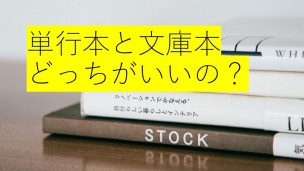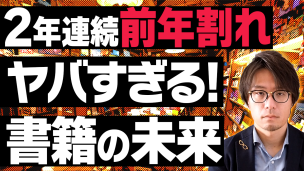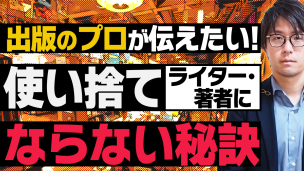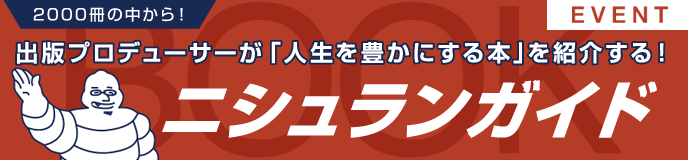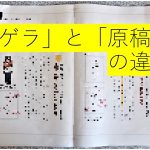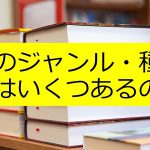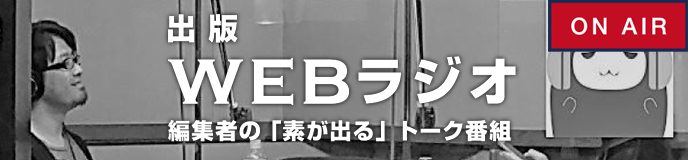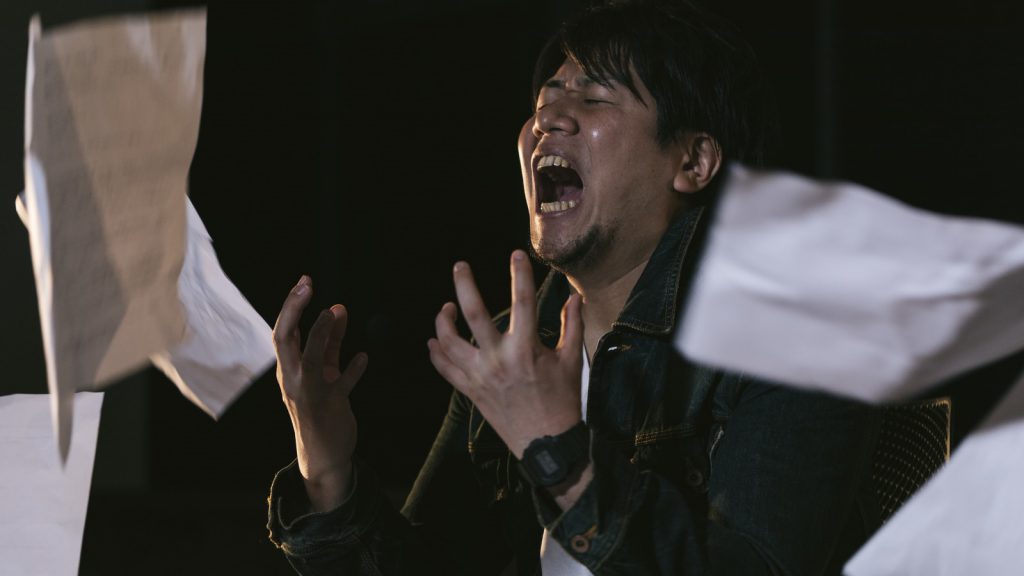
今年の暑さにやられているのか、単純な体力の衰えなのか疑問な出版プロデューサー西浦です。もう日本は7月~8月は休みにしませんか?それか夏場は昼夜逆転とか。夜9時出社して、朝5時に退勤して、朝ごはん食べて解散しましょう。で、夜まで寝ればいい。アフリカにそんな国があったはず。
さて、毎日更新92日目。
昨日今日と、出版相談をされたり著者と連絡を取っていて「出版においては絶対重要なこと」なんだけど「後からやると絶対めんどくさい」ことに向き合ってもらっています。
実際にクライアントに取り組んでもらっているのをはたから見て、すごく大変そうだなと再確認しています(笑)
これは広く出版TIMES読者の皆さんにも知ってもらい、事前に準備しておいていただきたいなと思ったので書きますね。
その「めんどくさいこと」というのは「実績の整理」。特に今までの合計ユーザー数と直近1年、2年のユーザー数の把握です。
セミナー講師、講演家、医療関係者、美容系など、ジャンル問わず必須なので、もうセミナーや診察の都度まとめておいてもらうのが理想です。
目次
「ユーザー数の把握」で得られるメリット
ユーザー数に代表される実績の整理がなぜ必須なのか?
それには2つの理由があります。一つ目は「プロフィールに書く」から。そして二つ目は「出版後の販売予測に使う」からです。
一つ目についてですが「今まで何人のお客さんや患者さんと向き合い、問題を解決してきたか」というのはすごく重要なプロフィール情報になります。
顧客数は多ければ多いほどエピソードも多いし、ノウハウも再現度が高く、支持され、クチコミされているから多くの人がその著者の元に集うのだと考えられます。
信頼度が高いと言ってもいいでしょう、とにかくユーザー数は多いに越したことはありません。プロフィール欄で最も重要な要素と言えるでしょう。
※ユーザー数が少なくてもクライアントに著名人が多い場合、その著名人の名前を出せるなら、この限りではありません。ネームバリュー次第です。でも結局はその著名人のファンの数など「数の論理」でカウントしているので、広い目で見ればやっぱり「ユーザー数は多いに越したことはない」ロジックなのですが。
次いで「出版後の販売予測に使う」という理由ですが、「どれだけ売れるか?」という期待値の高い企画は、出版社の会議を通りやすいし、広告などのチャンスも得やすいです。
特に販売予測に使う場合、今までの累計ユーザー数もさることながら、直近1年、2年の数字も重要です。
例えば直近1年で2000人のユーザーがいる著者なら、出版後の1年間にやはり2000冊は自分で売ってくれるだろうと予測できます。(出版社はその2000冊以外を売る)
それに2年前が1500人、1年前が2000人なら、今年は2500人?とさらに期待値は上がりますね。
逆に、累計ユーザー数が多くても、明らかにピークが数年前で毎年ユーザー減ってるような著者の場合、今年の売り上げ予測も暗いです。やはり勢いのある著者と組みたいというのが出版社の本心ではあるでしょう。
著者が把握すべきデータ項目
さて、このユーザー数ですが「今まで何名のお客様にサービス提供してきたか書いてください」と言うとけっこう「ざっくり」の人が多いです。
全く考えたこともないという人も稀にいるので、とりあえず「1年間の顧客数×開業年数」でざっくり計算してもらいますが、やはり「ざっくり」では不安です。
僕としてはもう少し細かく
- 年度毎のユーザー数推移
- ユニークユーザー数(合計ユーザー数でなく、純粋な顧客数)
- 販売されたテキスト数(イベントでの販売とweb上での販売と別管理)
などの項目を把握しておいて欲しいのですが、このレベルになるほぼゼロです。誰も把握されていません(笑)
本は通常、一人1冊買えば十分なものですので、合計ユーザー数より、ユニークユーザー数の方がよりデータとして有効です。
また講演会等で販売されたオリジナルのテキストがある場合、その販売数はそのまま「出版後のセミナーでの販売数」に予測変換されるのでかなり貴重なデータです。
これを例えば10年分、調べてくださいと言われたら、誰しも10歳ぐらい老けた顔になります(笑)
わかります、絶対めんどくさいですもん。3年でもつらい。
でも重要かつ有効なデータなので心を鬼にして、可能なかぎり正確なところを調べてもらいます。
これを楽にするには、エクセルでも何でもいいので、ユーザー数やテキスト販売数を管理しておくことです。
「ここを見ればわかる」というデータを作っておくのです。僕の場合はプロデュースした本の実績数をまとめたファイルを作っています。
そうするとこの数値が自分のKPIになり「どうやったらこの数値を上げられるか」と考えたり、サービスごとのユーザー数まで把握するようになって「メインの商品AよりBの方が時間対効果高いな」といった新たな経営指標の発見にも繋がるでしょう。テキスト販売金額バカにならないぞ、とか。
何度も書いていますが、出版は準備が9割なんです。
個人事業主の青色確定申告のように、年末に大慌てで処理するのではなく、毎月、あるいは毎週など、都度記録に残しておいてもらえると後が楽で良いと思います。