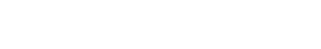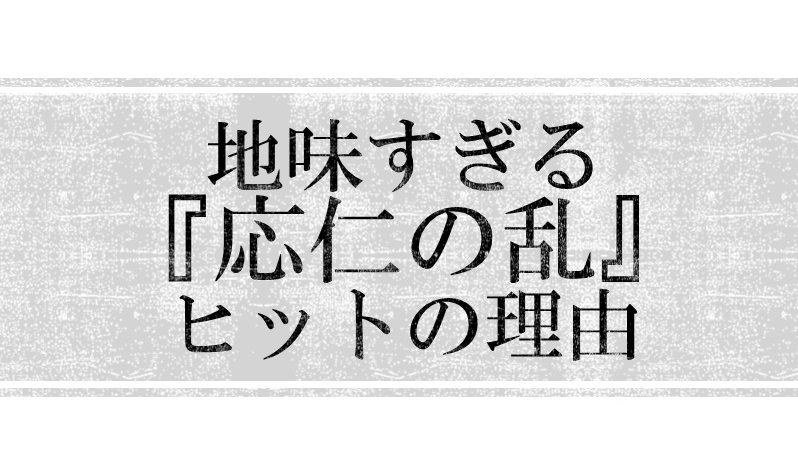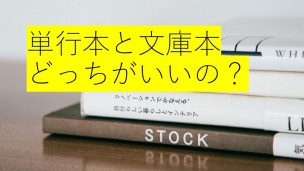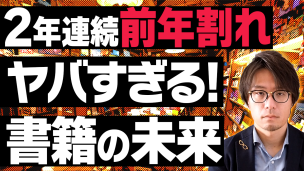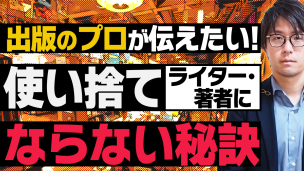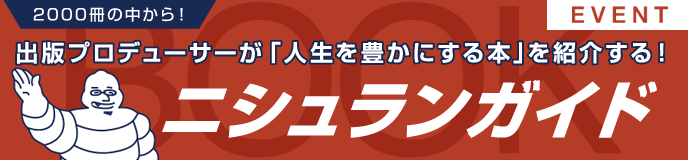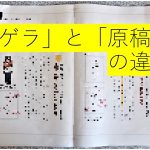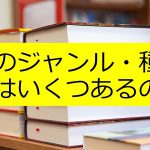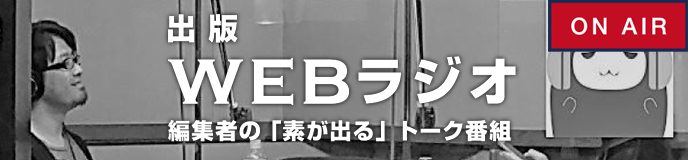ベートーベンの『運命』聴きながらこれを書いてます、出版プロデューサーの西浦です。
昨夜、大好きなマンガ『蒼天航路』の著者・王欣太先生のAfternoonTeaPartyに参加してきました。
先生が読者と交流されるのは実に16年ぶりで、ちょっともう何が起こったのか信じられないというか、今もふわふわしております。
最後に参加者一人一人と握手しながら話してくださったのですが…僕ちゃんと握手したよね?記憶にない!「お礼を言わねば」とそれだけで頭いっぱいで、それは確実に伝えたんだけど他は飛びました(笑)
ファンとしては作品のいろんな裏話が聞けて良かったし、それをすべてここに書きなぐりたいくらいなのですが、厳選して「作品作りにかける王欣太先生の流儀」をご紹介します。
(イベント内で話されたことは、個人名以外公表してOKとの許可を得ています)
※アイキャッチ写真はいつもお世話になっているギャラリークオーレ様よりお借りしました。
目次
脳は楽な絵を描こうとしてしまう
参加者の方が「先生の絵はすべて命がこもっているというか、兵卒の一人一人まで圧倒的なパワーを感じるのですが、それはなぜか」という質問をしていて、先生が「命込めて描いてますね」とおっしゃった上で作品作りの流儀を一つ教えてくれました。
曰く、「脳を裏切り続けること」が基本なのだそうです。
脳はどうしても楽な絵を描こうとしてしまう。
例えば剣で敵を斬るシーンであれば、歌舞伎で大見得を切るシーンのような構図を考えてしまう。
しかしあれはもう止まったシーンで、読者に次のページを繰らせる勢いがないのだそうです。
斬撃であれば、袈裟斬りを放った後よりも、その「最中」に一番パワーがこもっている。その瞬間を描かないとダメなのだそうです。(歌舞伎は動きでそれを表現できるから問題ないのだろうと思います)
たしかに斬った後のポーズって様になっていて奇麗ですが、「相手を切り殺した」という迫力に欠ける気がします。
それに、もう相手が斬られた後なので、こっちも「あ。斬った」とちょっと止まってしまうというか。
これが「今まさに斬っている絵」だと違ってきます。肉や骨を斬るために力を入れる「瞬間の筋肉」を描くことになりますし、そういう場合は血しぶきも変わってくるでしょう。
「うおおお!斬ったぁあ!」と、読者が次のページを繰る勢いを生みます。
自分が居合をやっていた時の話ですが、一度、真剣で斬らせてもらったことがあります。
先生のおっしゃった通り、斬った後というのは時間が止まりました。「ちゃんと斬れた」という安心感とか「真剣は切れ味がすごすぎる」という恐怖に放心するんですね。
しかし、斬りつけている刹那は、師範から「ためらわずに振りぬけ」と言われていたこともあり、とにかく両手に力を籠め、難しいことは何も考えずに、ただ刀を振り抜きました。
もし絵にするなら、切り払った後の放心した自分より、刀が目標に当たってから振り抜くまでの無心で斬っている自分を絵にしてもらった方が、絶対に迫力が出るように思います。
脳を裏切り続ける企画を
こういった「脳が楽しようとする」働きを裏切り続けることが絶対だと、イベント中何度もおっしゃっていました。
僕らも企画を考えていると「売れている類書」に、自分の企画を寄せてしまうことがあります。まさに「脳が楽しようとする」現象ですね。
絶対良くないことですが、まだマシかもしれません。ヒット作を真似している分、少しは売れる可能性があるからです。
最悪なのはその売れているものの逆張りをしただけという企画で(早起きしなさい!という本に対して「早起きは危険だ!」と言うだけの企画)、これはもう何もオリジナリティもない上に、売れた本を意識しすぎで、より売れません。
他に「脳が楽しようとしているなぁ」と思うパターンで言えば、
「普段本を読まない人が買うからベストセラーになる!」
⇒「だから初心者が読んでも面白いものをつくべき」
⇒「つまり『今までにないものを作りたい』というのは作り手のエゴ」
⇒「新しさ不要、分かりやすくつくる!」
⇒「結果、特に特長がなく売れない」
というのも「あるある」です。
「普段本を読まない人が買うからベストセラーになる」⇒「初心者が読んでも面白いものをつくべき」というここまでは正しいのですが、「初心者が読んで面白いもの」と「本好きが読んで面白いもの」を両立させようという工夫がそこにありません。脳が思考を停止していますよね、楽をしています。
出版のようにものすごい数の「類書」が存在する場合は、初心者向けであっても必ず「新しさ・オリジナリティ」の追求は必要です。だって初心者向けの本いっぱいあるんですもん。
初心者と本好きの両方を満足させなくてはいけない理由の一つがクチコミです。初心者は詳しい人のオススメを参考にしますよね。僕も例えばPC関連のことは詳しい友人に聞いて「これがイイよ」と言われたものの中からデザインの気に入ったものを買います。
だから初心者向けにモノづくりをするなら、詳しい人が「これはすごくいいモノで自分も使ってる(面白いと思ってる)し、初心者にも親切なつくりだからいいよ」と言ってもらえるのが理想です。
詳しい人が「よくある内容だし、俺はいまいちだと思ったけど、初心者にはこれくらいでいいかも」って薦めるものを買うのってなんだかちょっと嫌じゃないですか?
すごく価格帯の開きがある商品ならそれも選択肢としてあり得ますけど、本は差額が2000円以上になることはあんまりありませんから。
言葉の修業
ブログや日々の原稿書きもこれに似たようなところがありますよね、なんとなく「似たようなことを書いてしまう」もっと別の表現がありそうなのに、同じようなことを書いて終わらせてしまう。
「毎日書く」ことができるようになると、今度は毎日同じ時間内で今までよりも良いものを書く、読みやすいものを書くという工夫が必要です。
そう意識していないと、脳は楽をしようとしてしまいますね。「書けてるからいい」「読まれてるからいい」と。けれどそこで止まってしまってはダメなのです。
王欣太先生も「言葉」にはずいぶん苦労なさったそうです。というのも元々絵を描くことがお好きで、めちゃくちゃマンガ好きというわけではなかったそうなので。
最初から漫画家になりたかったわけでもなく、2位狙いで応募した賞がきっかけですごい編集者と出会って「この編集部に入れないかな」と思ったそうですから。(つまり一時期は編集者になりたかった!)
その編集さんと一緒に『蒼天航路』を作っていくわけですが、13巻くらいでその方が担当から離れてしまいます。
それまではこの編集さんと二人三脚というか、先生曰く「言葉のかなりの部分はあの人が作った」くらいビッシビシのセリフをこの編集さんが生み出してきたので、困ってしまうのです。「ならば良し!」なんてセリフはなかなか出てこないと。
そこからはもう自分でその人の言葉に追いつけるかの勝負だったとおっしゃっていました。
とにかくその編集さんの言葉のセンスをひたすら追ったと。「あの人なら何て言うか」と考えておられたそうです。「言葉の修業をした」ともおっしゃっていました。
また、マンガよりは同じ時代の広告関係の方、例えば糸井重里さんや中畑貴志さんのクリエイティブからもいろいろ吸収されてきたそうです。
まずは「毎日書く」ことが大事ですが、そこからは「言葉を磨く」ことがもっと大切になります。
王欣太先生のように素晴らしい編集者と出会って、仕事しながら言葉磨きをできると理想ですが、編集者と出会う前にも、僕らは言葉を磨いていかねばなりません。
そのために自分の憧れる作家さんや、面白いコラムニストさんの文章を真似るのもお勧めします。
日ごろから面白いものを読んでいる人が、面白い文章を書くのです。
そのためには「楽しようする脳を騙す」ことが必要ですね。
マンガも書籍もwebの記事も同じです。良いものを作ろうと思うなら避けては通れません。
そのために常に「本当にそうか?」と「世の中の常識」や「自分の常識」を疑い続ける必要があるのだと改めて思いました。
王欣太先生、貴重な話をありがとうございました!!