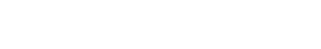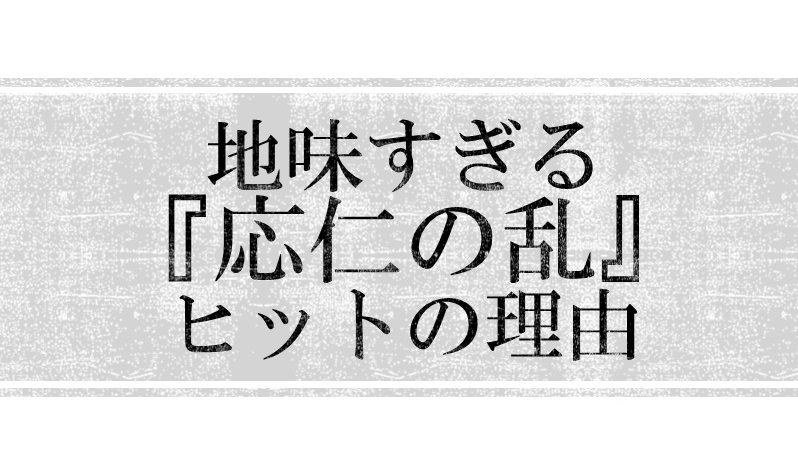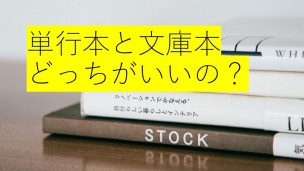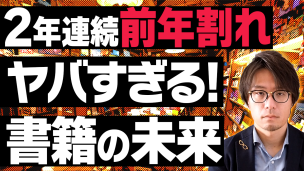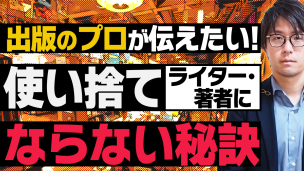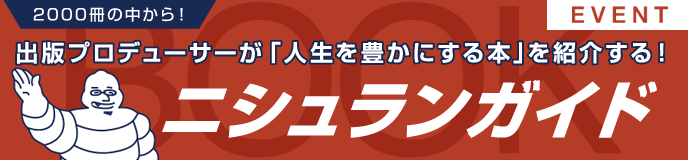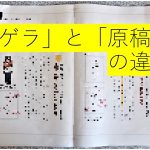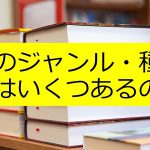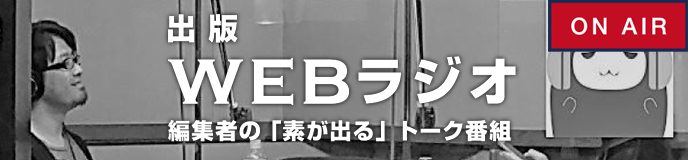たいてい40代に見られる30代の出版プロデューサーの西浦です。
実は2日前から体調を崩しておりまして、特に昨日はある業界のレジェンド的な存在(90代!)を取材させていただけることになっていたのに、体調が回復せず泣く泣く断念。取材はチームの他の方にお任せしてしまいました。(Kさん昨日はごめんなさい)
30代が寝込んでいるのに、97歳のレジェンドが現役バリバリの圧倒的パワーで取材を受けている。情けないですね。40代に見られるのも実年齢より不健康だからかもしれない…。
真剣に自分の健康管理をしなくてはいけないと思い出したのですが、そもそも健康情報ってどうやって集めたらいいのでしょうか。けっこう難易度が高いですよね。
目次
WELQ問題
少し前、DeNAのWELQ問題に端を発し、web上の健康情報の信ぴょう性について問題になりました。
ちなみにWELQ問題というのは、健康情報を扱うサイトWELQが検索時に上位表示される大きな影響力を有しながら、「肩こりの原因は幽霊かも」というような、およそ信憑性の低い記事が掲載されていたり、あるいは外部のサイトからコピーしてきた、いわゆるパクリ記事を掲載していたりというひどい運営を上場企業がやっていたという問題です。
これを機に、webメディア業界ではにわかにキュレーションメディアの運営を考えるというテーマがホットになりましたし、記事のPR表示をどう扱っていくべきかなど、勉強会も開かれ僕も参加してきました。
ちなみにこの時(2016年12月ごろ)はじめてwebメディアの勉強会に参加したのですが、「めっちゃ意識高いな・・・!」と感じました。
紙媒体の雑誌なら広告の他にタイアップ記事とか「広告に見えないけど実際は広告的な記事」というのはあるし、ある種これは「お約束」で「読者も分ってるよね?」という感じなんですが、
webメディアの方々はマジメに「広告はそれとわかるようPR表示するのが読者のため」「PR表示してても読みたくなる記事を書けばよい」という主張が多かったように感じます。
すべてのwebメディアがそうではないでしょうし、実際にWELQみたいなサイトもあったわけですが、全体的には健全な方向へ舵をとっていくのだろうと感じました。
その後「医者が完全監修」ということを明確に打ち出している記事が増えたり、逆に自主的に医療情報の扱いを中止したサイトも出てきました。
紙媒体で長くやってると、そのあたりの感覚は少しマヒしていたかもしれません。いい刺激になりました。
健康情報に関する古くからある問題
ただ、よく考えて欲しいのがそもそも「健康に関する情報の信憑性」については昔から問題があるということです。
例えば最も影響力のある媒体、テレビですが、健康は強いテーマで、視聴率も高いらしくよく取り上げられます。
TVの構成上、動きのあるモノや分かりやすいものが喜ばれる傾向にあるため『○●体操』とか「××を食べたら●●に良い」というような情報を切り取って発信しがちです。
体操はそこまで悪いものはないのでしょうが、何か一つの食材だけ摂っていれば健康になるというのはちょっと…ですよね。
本でもこういう「トンデモ健康本」はあって、良識ある人たちは「それはどうなの?」という姿勢です。
かといって「結局は健康は、部分ではなく全体で考えねばならないことだから、栄養のある食事と、適度な運動、質の良い睡眠が大事ですよ」なんて教科書のような回答を貰っても、読者としては「分かっちゃいるけど、それでどうしたらいいかわからないから困ってるんじゃないか!」と怒りを覚えてしまうでしょう。
いったいどうすればいいのでしょうか?
自分の不健康問題
僕はなぜか健康書のプロデュースを得意としていて、ヒット作もいくつか出ています。
自分でもなぜビジネス書等じゃなくて、健康書なんだろう?と思っていたのですが、ふと気づきました。
実は僕自身が筋金入りの不健康人間なんです。
15歳の頃にすでに不整脈をやってますし、ストレスで胃をやられて胃カメラも飲んでます。20歳でぎっくり腰、その後腰椎すべり症と診断。さらにお腹の冷え、胃腸の弱さ、副鼻腔炎など常にどこか悪いです。視力は当然悪いですし。
冒頭にも書きましたが、この2日間も体調不良で寝込んでます。(最近の流行りは胃腸で、下痢や胃痛、お腹の冷えですね。よく考えたら年に2回以上あるんですよ。)
20歳でやった腰が原因で、23歳の新入社員時代に「腰椎滑り症」と診断、それから毎年3~5日間は会社を休まねばならない状態でした。
いわゆる病院では「痛み止めを打って安静にしててください、腹筋鍛えてください、体重も増やしすぎないように。」としか言われませんでした。
仕方ないので、いろんな整体やマッサージをはしごするのですが、なかなか「治る」ということはありません。
時には腰を施術してもらってから逆にとんでもない痛みに襲われ、動けなくなったことも2回ほどあります。
腰の筋肉が癒着して、背骨の補佐をしていたのに、それをほぐしたことで、支えが亡くなり激痛が走ったのです。最長3週間くらい寝たきりでした。
けっこう絶望的な20代だったな…
「治してもらおう」という意識を捨てた
結局、今は治ったのかというと腰が治ったわけではありません。
でも「治してもらおう」という意識は捨てました。
自分のことは自分で管理せねばならないと思うようになったんです。
腰も痛み具合でまだイケるとか、これは針をうった方が良さそうとか、風呂上がりのストレッチでなんとかなりそうなど自分なりに対応しています。
おかげで腰については、最近は動けなくなるようなことはなくなりました。
僕自身が救いを求めてさまよった絶望の20代と、そこで学んだことや体験したことから「自己管理」に到達した現在があるからこそ「健康書」のプロデュースが得意になったのかなと思います。
病院で「痛み止めを打って安静にしててください、腹筋鍛えてください、体重も増やしすぎないように。」って言われたときの「それって、何のアドバイスもないのと同じじゃないか」という失望感とか、その後自分なりにいろんな整体院にかかったり本を読んだりして「自分に最適な対応方法」を見つけて行った経験があるので、読者の絶望感や暗中模索感、希望を求める気持ちがすごくよくわかります。
その上で「どういうレベルのアドバイスが欲しいか」「どういう種類の方法論が知りたいか」という勘どころがなんとなくわかります。大切なのは自己管理、自分でなんとかできる方法です。
自己管理のための健康本を
腰痛一つとっても、人によって原因や症状は違いますから「こうすればすべての腰痛がなくなる」ような方法は「普通に」考えたらありません。それこそ「腹筋鍛えて、体重を増やしすぎないように」というような当たり障りのない方法になる。
しかし腰痛の症状を緩和する方法として比較的みんなに効果のあるマッサージはあるなと感じますし、あお向けに寝る時膝を立てるだけで、腰が地面にしっかりくっつけられたり、ちょっとしたことで楽になれる方法はあります。それに、常識とされていることの穴をつくような知識もあります。(姿勢は必ずしも完璧に良くなくても良いとか)
僕は医療関係者ではないので、ちゃんとした理論をもとに言えませんが、その道で10年20年と続けてきた方だからこそ言える知識や「たいがいはこれでOK」という方法論が存在することは確信しています。
プロの医学的なエビデンスをベースに、10年20年、あるいは数万人数十万人を見てきたという経験値から導かれる、「普通を越えた健康知識」です。
それらをわかりやすく伝えて「自己管理」に活かしていくことが、正しい健康書の役目なんだと思っています。
健康問題について世の中が敏感な今だからこそ、プロの医療関係者には「とんでも健康書」でもなく、「ありきたり健康書」でもない「自己管理のための健康書」を書いていただきたいと思っています。