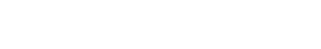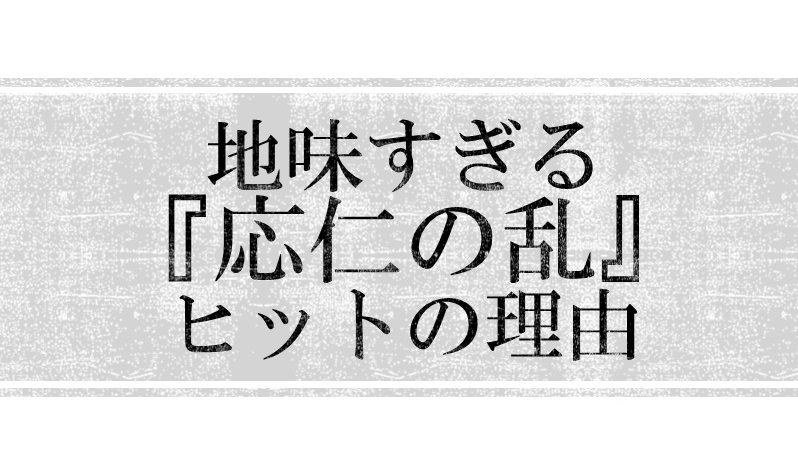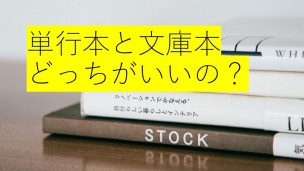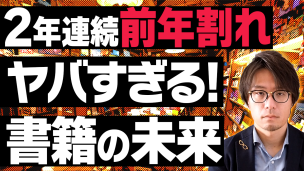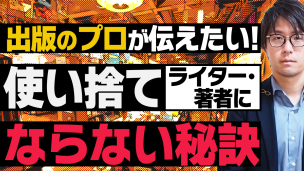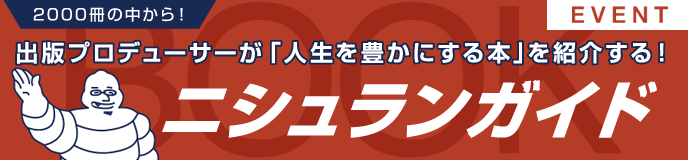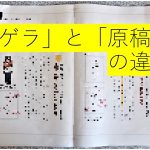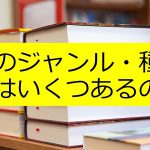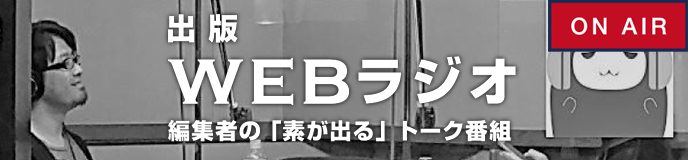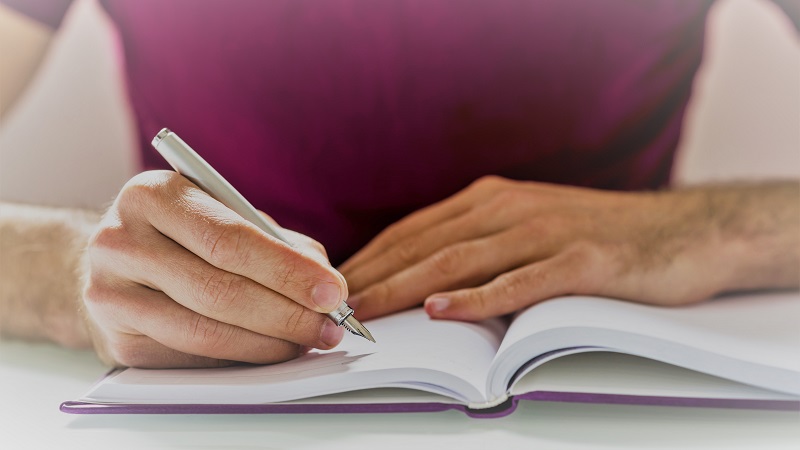
大好きな作家さん「カレー沢薫」先生が最近、「飲むヨー」こと「飲むヨーグルト」にハマっていて、
ちなみにローソソはグリーソスムージー系が抜きんでている。スムージーなど意識半端に高い系のOLが3日で飽きるものと思っていたが、その先入観を粉砕してくれた
と言うので、「意識半端に高い系OLだけに楽しませるわけにはいかん」と今朝買ってきて後悔してる出版プロデューサー西浦です。
もっとフルーシ感の強い方にすればよかったです、先生・・・。
毎日更新99日目、今日はそのうち書こうと思ってた編集さんに教えてもらったシリーズ第一弾「ワニブックスの編集者Uさんに教えてもらった文章術」です。
ワニブックスのUさんと著者と打ち合わせをしていて、文体についてのアドバイスを頂きました。
こういう編集さんからの生アドバイスってすごく参考になるのでシェアしますね。
目次
寄り添うようなウィスパー文
いざ出版!となると肩に力が入って「である」調になったり、「あれ?著者って剣道の師範だっけ?」ってくらい大上段に構えた文章を書いてしまいがちです。
いわゆるカタイ表現が続くと、読者は読みづらいので、基本的にカジュアルで読者に語り掛けるような文体が良いです。
かりにカタイ内容の本だったとしても、文体まで固くする必要はありませんし。
具体的にはお客さんに実際に話したり、説明してる時の音声を録音しておいて、それを少し整えると感覚的につかめるでしょう。
会話では、相手に理解してもらえないと先に進めないので、無意識で「分かりやすい表現」を心がけているものです。
とはいえ、話し言葉そのままでは、読みづらい部分もあるので、あとで読み返してリズムがおかしくないか確認・修正しましょう。
ちなみに普段から難しい本を読むのが好きな方や、先生と呼ばれる仕事の方もこの傾向にあるのでお気を付けください。
【文章術その1】
- 自分の話し言葉を録音してみる
メソッド化する
非常に良いことが書いてあるんだけど、特に役に立たない文章というのは案外多いです。それはメソッド化まで進んでないからだと思われます。
「そんな理屈は分かってるんですよ!こっちは具体的にどうするかっていう『ハウツー』が欲しいんですよ!」って読者に厳しい意見を言われる本ですね。
企画やアイデアなど「頭の中のこと」こそ、具体的なメソッドにしないと読者は満足してくれません。
「佐藤可士和の超整理術」 はクリエイティブ系の話をカバンの整理、書類の整理という「具体的に実行できるハウツー」に落とし込んだから売れたと考えます。
ですので、考え方や、属人的なスキルであってもなるべく具体的なメソッドに落とし込みましょう。
簡単な方法としては『〇〇する』という「そのままやればOKな行動として表現する」ことです。
例えば「適度な睡眠を心がける」ではメソッドとは呼べないので「23時にはベッドに入り、自然と目覚める時間を記録する」として適正な睡眠時間を計算できるようにしてみるとか。
そうなると今度は「23時にベッドになんて入れるかよ!」っていうツッコミが来るので「22時には風呂に入る」とかドンドンハウツー化してしまいましょう(笑)
こうすることで自然とハウツー、メソッド化していきます。
でもちゃんと自分やお客さんが実践されてるハウツーにしてくださいね、本当に不可能なノウハウはノウハウとは言えません。
【文章術その2】
- 「〇〇する」という、そのままやればOKな行動として表現する
新しい考えと極論は力がある
「なーんか読んだことあるなぁ」という内容の本はもう最後まで読むのがつらいですよね。やはり主張に「新しさ」が必要です。
読者にとって「知っていること」というのは読む価値がないんですね。「知っていることと、出来ていることは違う」というもっともらしい意見もありますが、それはこちらの甘えかもしれません。
僕も著者の話をヒアリングしたとき、すでに聞いたことがあるメソッドや知識ばかりだと「マズいな…」と思い始めます。
この場合は差別化ポイントを探すのが手っ取り早いですね。僕の企画はここが半分以上を占めています。ひょっとしたら実質9割くらいここに力を注いでいるかもしれません。
得意なんですよ、ヒアリングして、その人の優位性見つけるの。
ポイントはその人が何年も生き残ってこれた理由、選ばれてきた理由を掘り下げることです。
生き残ったということは、それだけの実力がある証拠ですし、選ばれたということは他とは違う部分があるはずです。
具体的には「なぜうまくいかない人がいるのか?」と質問します。
うまくいかない理由をどう分析しているかで、その人のオリジナリティが見つけやすくなります。
また、ちゃんと実績を出してきているので、そのうまくいかない理由をクリアする方法もハウツー化しているはずです。
この差別化とメソッド化を突き詰めていくと極論が出てきます。
「極端な話、〇〇さえすればだいたいOK」「極論ですが△△は不要です」と言った言葉が出てくるようになります。
これはかなり強いです。「~が9割」っていうタイトルの本が一時期増えましたが、それくらい極論は強いのです。
突き詰めていない、ただの極論は「おいおい、極論言うなよ」と読者に鼻で笑われかねませんが、しっかり理論が構築されメソッド化された果ての極論であれば「なるほど、真理かもしれん」「一理はある」と納得してもらえます。
【文章術その3、4】
- 「なぜうまくいかない人がいるのか?」と問う
- 突き詰めた先で極論を言う
いかがでしょうか。文章術の向上に役立てれば幸いです!