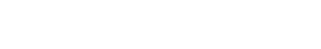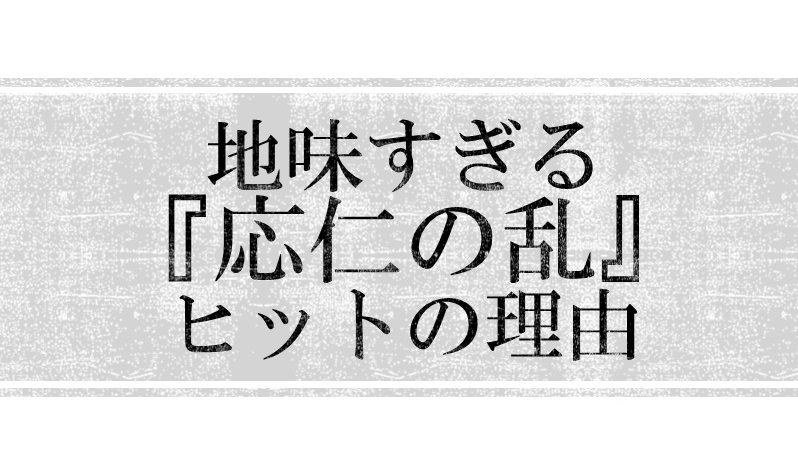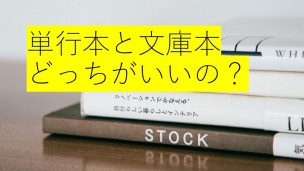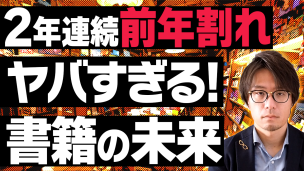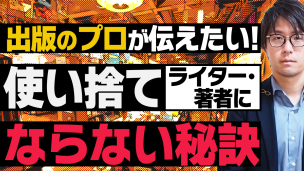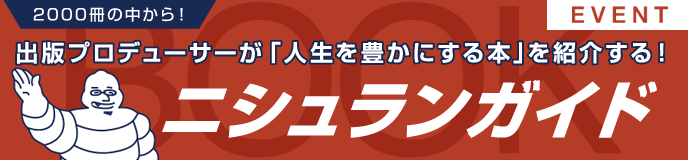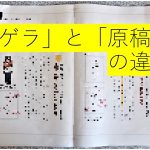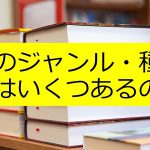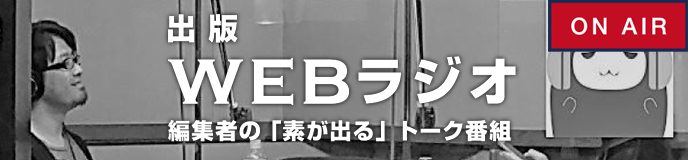お気に入りのロックな黒Tシャツに、アンパンマンの赤が色移りしてブルーな出版プロデューサー西浦です。
いやね、畳んだTシャツをアンパンマンのおもちゃの上に置いてたんです。室内はずいぶん熱かったんでしょうね、アンパンマンの鼻が溶けて服に塗料がついちゃったんですよ(涙)アンパンマンは水に弱いけど暑さにも弱いようです。
さて、毎日更新98日目!
目次
あなたの「ママさん像」合ってますか?
西浦は今は健康や美容・ビジネスなど「一般書」と呼ばれるジャンルを主に扱っておりますが、学研時代は1年だけ児童書のマーケティングを担当していました。といっても入社2年目で異動してきたペーペーとだったので特に何にもしてなかったんですけれど(苦笑)。
その時の上司の方針で「とにかく書店に行って、何かをつかんで来い」と毎日関東近郊の書店さんに行ってました。当時はまだ自分に子供もいなかったし、もともと興味のあるジャンルでもなかったので児童書を買う人のことが全然わかってなかったのでありがたかったです。
店頭で立ち読みしてる人を見つけては、探偵(ストーカー?)のように尾行し、何を手に取るのか?何を買って、何を買わないのか?遠くから観察してました。
ある時は、子供に読み聞かせながら「うーん、なんか読みにくいね。違うのにしよう」と絵本を棚に戻すのを見て「読みやすいリズムが大事なのか!」とビックリしたり。
この経験で一つ知ったことがあります。それは誰しも偏見や思い込みで物事を見てしまうということ。
当時の僕には、「児童書を買うのは、いかにもな教育ママ」だろうという思いこみがあったのでしょう。教育ママとは真逆のイメージの、明らかにヤンキーっぽいご夫婦が一生懸命に児童書を選んでいるのを見て「自分の読者イメージは偏りがある」とはっとしたのを覚えています。一瞬自己嫌悪に陥りました。
読者のことを乏しい想像力で断定してはいけないのですね、自分の狭い世界で「児童書を買うお母さんはこういう人」という思い込みがあったと気づきました。
自分が親になって、いろんなお母さんのことを知るようになってそんな偏見は無くなりましたけどね。
これは今、一般書のプロデュースをするのにも通じていて、著者の中でも「お客さんと直接触れていない人」の企画はけっこうキケンだと思うのに非常に近いです。「読者はこうだろう」という思い込みで書いてしまって売れないケースが多いのです。
児童書は「古参が強い」分野だが
当時から「児童書はロングセラーが新刊より売れる」市場で、それは今も大枠では変わらないのでしょうが、最近、自分が親になって別の潮流に気づきました。
それはロングセラーでも「進化し続けているもの」が強いということです。
娘(2歳)が保育園で歌を習ってきて、それを自宅でも歌っています。ある日、聴いたことのある歌詞の、しかしはじめて聴く歌を歌っているのです。
それは『はらぺこあおむし』の読み聞かせ歌でした。
「はらべこあおむし」のお話がほぼそのまま歌になっているCDブックで、調べたらyoutubeではたくさん動画がアップされています(著作権上問題あるものが多そう)。
とにかくこの歌が好きで、家に帰ってくるとこの曲をせがみ、うたを聴きながら絵本を開くのです。最後の「あ、ちょうちょ!」のところがお気に入り。
これはプロモーションとしてかなり強いです。
子どもは狂ったように同じことを繰り返します。毎日毎日、何度も何度も同じものを読み続け、聴き続け、見続けます。しかも毎度嬉しそうにしています。
その状態の娘を連れて本屋さんに行ったら、なんと『はらぺこあおむし』のミニサイズ版やら幼児向け知育玩具やらがフェア展開されているではありませんか。そりゃそんなお宝、一度目に入ろうものならもうその場を離れません。
親も毎日読んでいるのを知っているし、ミニサイズ版なら自分でも開きやすかろうと躊躇なく買います。買わないとその場を離れないし。どの本がいいか分からない親にとって「本人が気に入っている」というのはすごく強い動機です。
「そんなに好きならいいよ」と、すでに通常版を持っているのにミニサイズ版を買うわけです。
ネット・保育園・書店の三重奏は強い
この「はらぺこあおむし」の動画はyoutubeなどでたくさんアップされていますが、他にも『アンパンマン』『だるまさん』シリーズの動画があがっています。(マルマルモリモリも良く出てくる)
アンパンマンはテレビ番組をほとんど「観せていない」のに好きになりました。保育園で「とんとんとんとんひげじいさん」の代わりに「とんとんとんとんアンパンマン」という替え歌で遊んでいるからかもしれません。
「だるまさん」はちょっと説明がややこしいのですが、3冊目の『だるまさんと』に登場する「いちごちゃん」が好きで見たがります。なぜかというと果物のイチゴが好きだからです、だるまさん関係ない(笑)
とにかく、今は歌や動画でプロモーションされると親としては回避するのがかなり難しいです。特にネット(youtube)と保育園と書店の三方から攻められると、もう買う以外の選択肢がありません。
もちろん「スマホもTVも一切見せません!」というご家庭なら関係ないでしょうが、それでも保育園やお友達経由で知っていくのでしょう。
ちなみにAmazonPrimeの「アマゾンキッズしまじろうと遊ぼう」も良く観ているので、一度退会したチャレンジを再会しようか?といった話にもなっています。
適応するもの
講談社がかつて撤退した「ボンボン」を『ボンボンTV』というyoutubeチャンネルとして復活させ、わずか2年で黒字化に成功、チャンネル登録者数も127万人を突破した(当時)という記事がありましたね。(記事最下部にリンク)
今の子供たちはTVよりもyoutubeを観ているという時代背景が、その成功要因の一つです。
さらに未就学児を対象とした兄弟チャンネル『キッズボンボンTV』も誕生し、2018年5月時点で登録者数が16万人だそうです。
僕が児童書のマーケティングをしていたのは2006年、7年くらいのことだったと思います。当時と今ではネット上のコンテンツ環境が大きく変わっています。
ネットユーザーが作った動画など、二次創作物は基本的に著作権法上の問題があるわけですが、上記のような強いプロモーション効果があるのも事実です。
僕個人としては結果的に紙の本が売れるなら良いのでは?と思ってしまいます。もちろんけっこうひどい二次創作もあるので、どうしてもダメだ!という場合は『ボンボンTV』のように自社でオリジナルコンテンツとして配信するのがよいと思います。
この児童書の動画プロモーションは全く新しいチャレンジなどではありません。
新しいものを作ったというよりは、すでに広がった文化(ネットで動画を観るという文化)に、すでに人気のある異業界のコンテンツをしっかり対応させたということ。
これはそこまで難しいことじゃないし、そこまで新しいことじゃないです。
だからこそ、受け入れられやすい、ものすごく大きな力になる。大人数に届く施策になり得ます。
(もちろん簡単・誰でもできる、という意味ではない。センスが必要でしょう。)
出版業界ではある種の「聖域」だった児童書も、環境の変化に対応していける作品とそうでないものとで、今後明暗が分かれるかもしれません。
児童書志望の編集者は今後、歌や動画づくりの才能を磨いていくべきかもしれませんね。
(参考)
講談社「ボンボンTV」、華麗な復活劇の舞台裏 漫画編集者はユーチューバーを志した