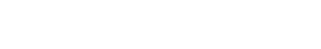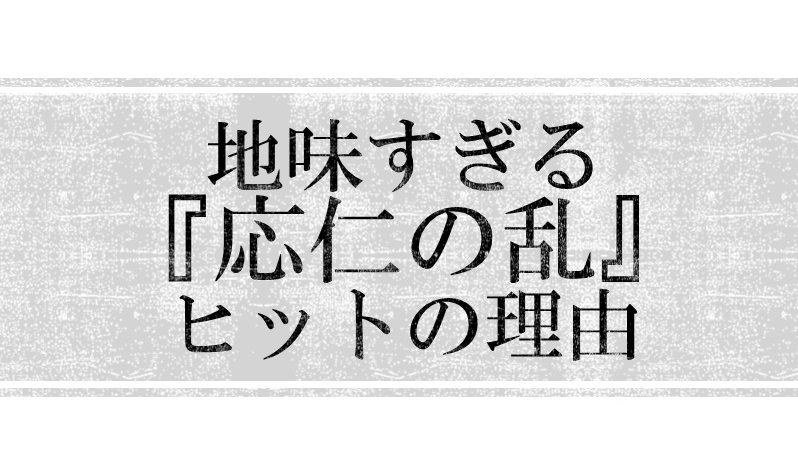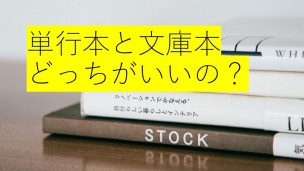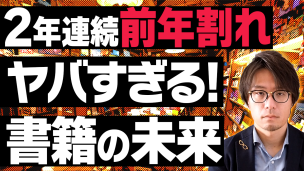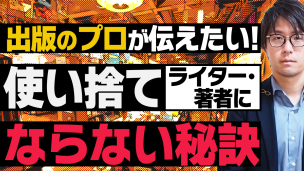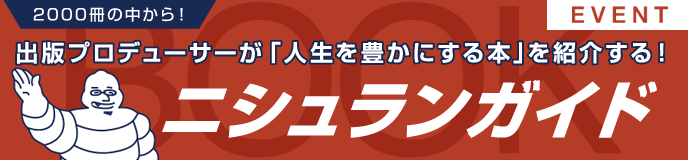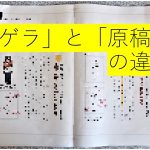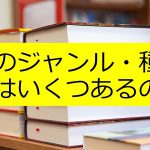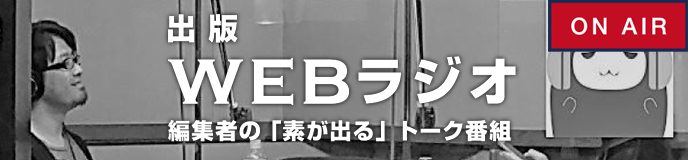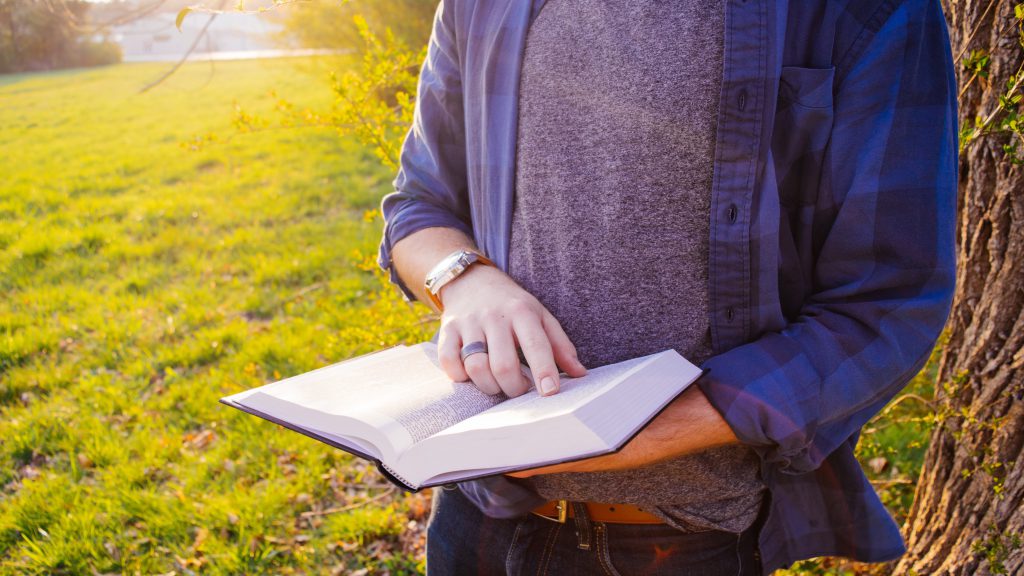
「雨降りそうだから洗濯物取り込んでください」と言われて取り込んだ後、雨降らないのが3回続いている出版プロデューサー西浦です。洗濯物に「またかよー?大げさなんだよ」って思われてそう。
さて、今日は出版の企画が進み、原稿を書き始めてから行われる「原稿へのフィードバック」について、出版プロデューサーの僕が何をしているのか書きます。
実は今朝も原稿へのフィードバックを送ったばかりなのです(笑)
目次
原稿へのフィードバックとは
この原稿へのフィードバックは、ふつう著者と編集さんとで行われます。
あれ?じゃあ出版プロデューサーが必要か?というと、実はいなくても良かったりします(笑)
実際、編集さんのように赤入れしてみたこともあるのですが・・・明らかに編集さんの方がレベル高いわけです。当たり前です。
じゃあ、無駄だからやらないという考えもあるのですが、「せっかく編集者じゃなく、元営業なんだから、営業目線と読者目線でコメントしよう」とやっています。
三人そろえば文殊の知恵と言いますが、それは三人が別々の目線で知恵を出し合うからこそ有効なのです。同じ目線で出しあうなら本当に無駄です、優れた方がやれば良いのです。
具体的には何をやっているのか?
それは
- 「良い部分の指摘」
- 「文全体の個性を指摘」
- 「強い言葉へのとっかかり」
を著者に伝えることです。
「虫」目線のフィードック
すべての編集者がそうではないでしょうが、多くの方は原稿が全部(あるいはある程度の量)そろってから一気に赤入れされる方が多い印象です。
そちらの方が効率も良いし、原稿全体を把握したうえで「鳥の目線」で編集できます。木を見て森を見ずでは本全体としての完成度が低くなってしまいますしね。他にも多くの担当作を抱える編集者はどうしても校了に近いものから対応することになるので、まだ日程に余裕のある企画にまとまった時間を取れないという現実問題もあります。
このやり方は上記のようなメリットがあるのですが、著者目線で見るとデメリットもあります。
僕がプロデュースしている著者の多くは新人さんなので「この書き方でいいのか?」という迷いがどこかにあり、迷いながら書くことになってしまうのです。
処女作やはじめての編集さんとの仕事は「あ、こういうことか」と著者が何かをつかむまで、やりとりの回数を増やした方が原稿の質が上がります。
だからこの部分をプロデューサーである自分がやることにしています。森を見るのは編集さんに任せて、森の中に入ってしまおうということです。虫目線ですね。
文章の良い部分を褒める
原稿を送ってもらって1週間後くらいには「良い箇所」を指摘して返します。この表現良いですよ、この書き方分かりやすいですねという肯定です。
著者によってはやはり「本はちゃんと書かなきゃ!」と思ってすごく肩に力が入っていることがあるので、普段通りの文章になっているところを褒めたりします。「あ、こういう感じで良いのか」と安心してもらうためです。
他にも読者が反応しそうな部分、初心者にわかりやすい例え話など、良い文章表現を見つけては返します。
何より褒められたり、頻繁にレスがあると人はやる気が出ます。モチベーションアップ効果が一番かもしれませんね。
部分の傾向から文章の個性を褒める
部分的に個性が出てくると「文章のリズムが良い」「エピソードが豊富」「最新の情報が多い」「網羅的に解説できている」など本人の個性が出てきますので、そこを指摘します。
自分の強み、自分の文章の良さって案外気づかないものですから、これは他人から教えてもらうのが一番です。
自分の個性が分かれば、それを活かす書き方に軌道修正していけるます。
強い言葉へのとっかかりを伝える
最後に「強い言葉へのとっかかり」ですが、これはちょっと変わっています。
まず文章ではなく単語や、せいぜい1行単位で探して光を放っている部分や、磨けそうな箇所を見つけます。
それを「もっと磨いて、キャッチコピーや名言集に掲載されるような言葉に出来ないか」提案するのです。
僕は5万部、10万部を越えていくには「クチコミ」がカギだと思っていて、そのためには「クチコミされやすい箇所」が必要です。
これは実感として原稿を読んだ時に、家族や友達に「ねぇ、知ってる?●●って実は〇〇なんだってさ」ってついつい言いたくなるかどうかです。
分かりやすい文、読みやすい文、理解しやすい文が「ついつい言いたくなる言葉」ではありません。
短くて覚えやすい、簡単で使いやすい、そして衝撃のある文が「ついつい言いたくなる言葉」です。
クチコミは、聞いた側が「へー、そうなんだ知らなかった」って言うだろうな、と予測できるからこっちは言いたくなるわけで、そういう言葉になっていないといけませんね。
こういった言葉は狙って作るのは難しいですが、コツがないわけでもないので、脱稿までの3ヶ月ほどで一緒に磨きをかけます。
つまり僕のイメージとしては編集さんが森を編集する前に、その著者らしい部分を増やしたり、きらりと光る木を大きく成長させつつ増やしておいて、準備万端にするためのフィードバックでしょうか。ですのでゲラになってからはほとんど赤入れしません。そこは編集さんを全面的に信頼するのが自分のスタイルです。
これをやった方が今のところ売れているので、効果があるのだと思っています。