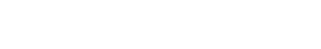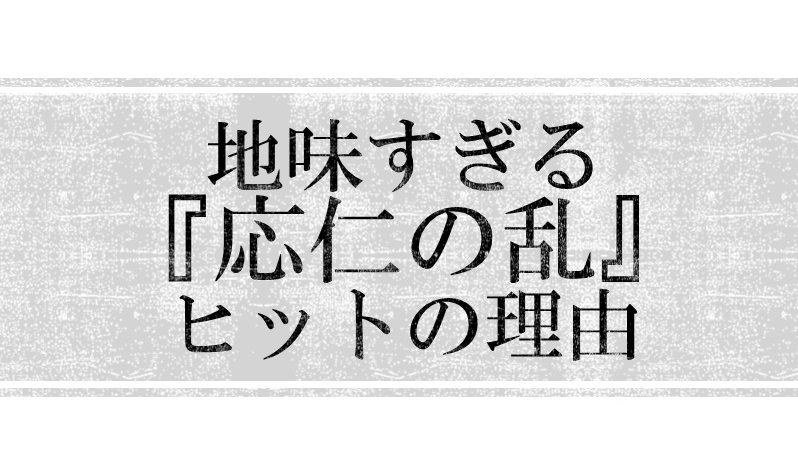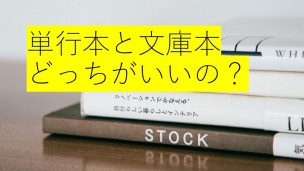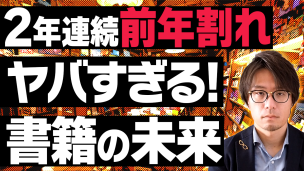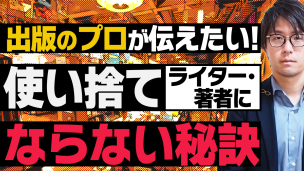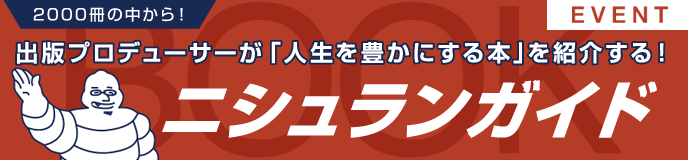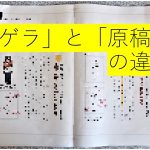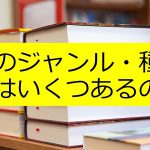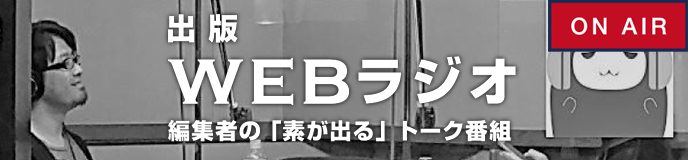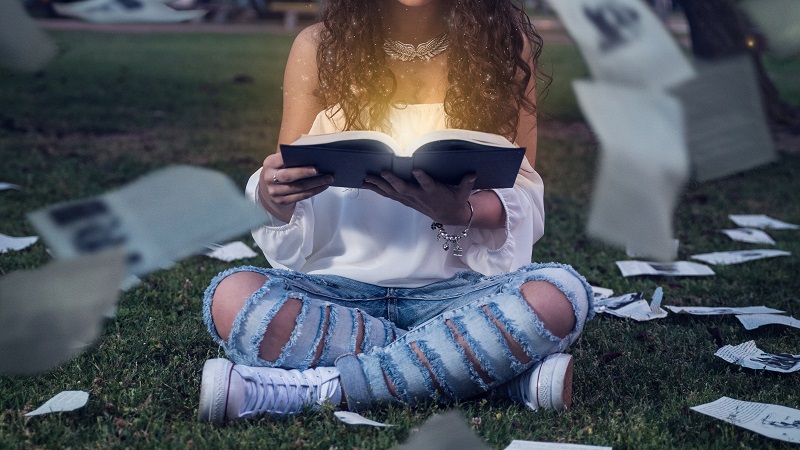
子どもには絶対「本を読め」と言わないでおこうと思ってる出版プロデューサー西浦です。父親が本好きで「読め」って言われてた子供って、たいてい読書嫌いなんですよねー。(つまり本音は読んで欲しいと思ってるので、どっちにしろウザがられるかもしれない)
今日は今朝読んだ
という記事と「図書館の自由に関する宣言」の問題、さらに読書コミュニティについて考えます。
※翌日こんな記事が出ました。
担任に伝わる情報は、それぞれの本の貸出回数と、そのクラスの各児童がどれくらい本を借りているかといった数値だけです。児童が読んでいるジャンルや本のタイトルなどの具体的な内容は伝わっていません
とのことでした。
目次
年間142冊読む小学校のヒミツ
埼玉にある彦郷小学校では、全校生徒の平均読書数が年間142冊にものぼるそうで、全国平均の約37冊と比べても非常に多いです。
ていうか出版社の人間の年間平均より多いんじゃないかな。
小学生は「朝読」活動で毎朝本を読んでいたり、電車通学の場合、社内で騒がないように「電車の中では本を読みましょう」と指導している学校もあって、中高生と比べても読書量は多い傾向にあります。
とはいえ彦郷小学校の142冊という数字は尋常じゃないです。
それを可能にしたのが「図書館のデータベース化」で
児童ごとの読書傾向を学校側が把握できるようになり、今どんな本を読んでいるのか、あるいは1ヶ月で何冊の本を読んでいるかなどを的確に把握できる
ようになったそうです。
そしてそれらのデータ資料を担任の先生に配布することで、個別指導を行ったり、時にはオススメの本を推薦することもできるのだそうで、このことに関して鈴木校長は次のように述べていました。
「『本を読みましょう』とクラス全員に向かって訴えても、なかなか効果は期待できません。それよりも、一人ひとりの読書傾向を先生が理解した上で指導すれば、児童の読書意欲も随分と上がってくるんじゃないでしょうか。」
クラス全員に訴えるより、一人ひとりに個別対応した方が大きな効果があるのは納得できます。その分すごく手間もかかるわけで先生方の熱意には頭が下がります。
データベースの利用のみにとどまらず、校舎の隅っこに設置されがちな図書館への導線を設計したり、「読書ビンゴ」で自分にとってなじみの薄いジャンルの本を読めるよう工夫したり、「ビブリオバトル」を導入してより質の高い読書体験をもたらすなどやはり非常に熱心に取り組まれています。
読書のプライバシー問題
ただ、周りの反応を見るに否定的なリアクションもありました。
最初に引用した『児童ごとの読書傾向を学校側が把握できるようになり、今どんな本を読んでいるのか、あるいは1ヶ月で何冊の本を読んでいるかなどを的確に把握できる』という部分が『図書館の自由に関する宣言』に抵触するのではないかという反応ですね。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
1.読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。
ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
とあり、たしかに児童ごとの読書傾向を学校側が把握するのは問題ないのか?と疑問も湧きます。
学校内の図書館はあくまで学校が運営しているから抵触しないとか?自分の通ってた小学校は「図書室」って読んでたし、学内の図書館と一般的な図書館って別なんですかね。その辺詳しくないのでちょっと調べてみました。
まず学校の図書館は「学校図書館(school library media center)」といい(まんまだった)、国立図書館(national library)、公共図書館(public library)、大学図書館(academic library)、専門図書館(special library)と並び、図書館の種別の一つです。
学校図書館は、学校のカリキュラムを支援し豊かにすることを目的として設置されるもので、日本では「学校図書館法」により、すべての学校に図書館の設置が義務づけられています。子どもたちが生きていくうえで必要な情報獲得能力を身につけるとともに、読書の楽しみを知る手助けをする重要な役割を担っています。
とあります。(赤字は筆者が意図して反映)
つまり図書館の一つだから、図書館の自由に関する宣言は適用されますが、今回の件は「読書の楽しみを知る手助けをする重要な役割」に則っているという考え方なのでしょう。
さらに『学校図書館法』をみると
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
とあり、学校が学校図書館を運営している(学校図書館は学校の内部)といえます。
よって「児童ごとの読書傾向を学校側が把握する」ことは、内部での情報活用であり「図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。」という図書館の自由に関する宣言に抵触してはいないということなのだと思います。
※ただ、法律については素人なので、もし間違って理解していたら、どなたか詳しい人教えてくださいませ。
読書傾向の把握に関する居心地
では本件が『図書館の自由に関する宣言』に反していないとスッキリしたところで、どう思うか?というと「なんかヤダ」という人が多いのではないでしょうか?(笑)
僕も生徒だったら嫌です。自分が何を好んで読んでいるかは、人に知られたくないなと思います。自分の本棚を見せるのって、自分のAVアーカイブを公開するようなもので、どんな羞恥プレイだよと。(と言いつつニシュランガイドっていうイベントで部分的に羞恥プレイしてるのですが)
ただ、この方法によって生徒の読書量が全国平均の3倍以上になったのは事実で、効果を認めないわけにはいきません。
出版不況の現状を考えれば、歓迎すべきことです。
でもやっぱり読んでいる本を管理されるのは抵抗がありますよね~。
たとえばこのデータベースを自分で管理できるようなアプリにしたらダメなんでしょうか?
ジャンルや作家の属性ごとにタグで管理できて、同じタグから次の本を探したり、個人は特定できないけど学内で読書量トップ10の子たちの人気タグとか、同学年で一番流行ってるタグの本を読んでみようかなとか。
「読書ビンゴ」で自分にとってなじみの薄いジャンルの本を読めるよう工夫する(強制でない前提で)という部分や、導線設置(ブックストリート)の工夫にはすごく共感するので、データベースの運用面だけ工夫すれば「なんかイヤだ」感もなくなるのかなと。
そのために図書館の本すべてにタグを付けなきゃいけないっていうコストが発生しますが、そのタグ付けは生徒が自分でやればいいんだと思うんです。そしたら読書感想文を書く訓練にもなると思います。ふざけたタグを付ける子もいるでしょうが、その感じ方や表現も自由のはずだし、規模を大きくしていけば最終的にそんなおかしいタグばかりにならないでしょう。
大人の読書コミュニティ
今回の記事を読んで思ったのが「これだけ本を読んでいた子たちも、進学して高校生になるころには本ではなくスマホに移行するのだろうな」ということです。
「朝読」活動や、その他の活動により生徒の読書量は増えているのですが、成長の過程でみんな離れていくんですね。
もちろん今回の記事で取り上げられた学校の生徒たちが大人になったときのことはわかりませんが・・・
僕は大人こそもっと本を読めばいいのにと思っています。
人は言葉で思考する生き物であるため、知っている言葉が多ければ多いほどより正確に自分の感情を言語化して自身を納得させたり、あるいは相手に自分の考えを的確に伝達することができるでしょう。
と記事にもありましたが、本をたくさん読んできた人は「他人の言葉」をたくさん吸収してきたおかげで、逆に「自分の言葉」「最適の表現」ができるようになると僕は感じています。
同じものを見ても「その人特有の感じ方、考え方、表現ができる」
それはその人のおかげで「世界を違った景色としてとらえることができる」というステキな体験です。
それを教養と呼ぶのだと、ある本から教わりました。
「あなたはどう思うの?あなたはなぜそうするの?」と質問して「なんかどこかで聞いたことのある言葉」が返ってくると、僕は残念な気になります。
「ああ、この人らしいなぁ」と思える言葉に出合いたいのです。
大人のための読書コミュニケーションや読書コミュニティをつくるにはどうすればいいのか。日々悩んでいます。
本好きが本好きだけで集まるんじゃなくて、「本は興味なくもない」っていう感じの方が「本を読むのが楽しくなる」コミュニティです。
なんかないですかねぇ。。。