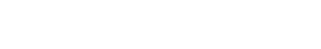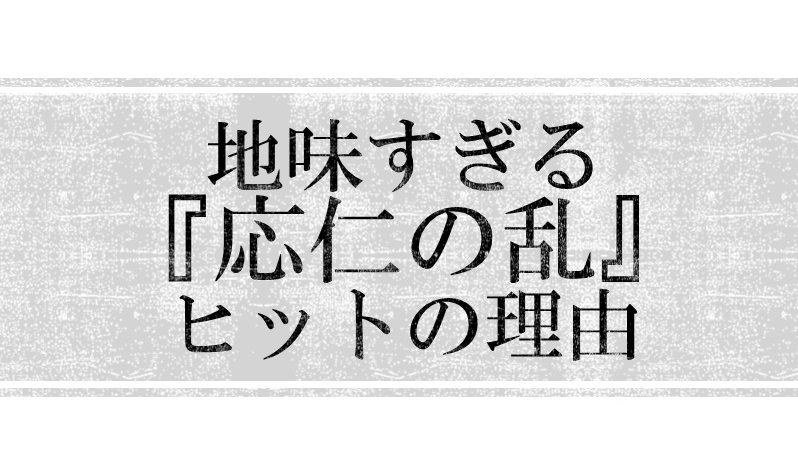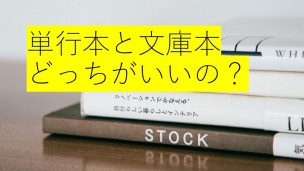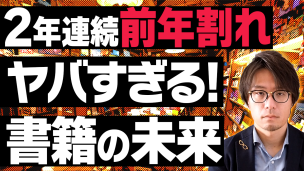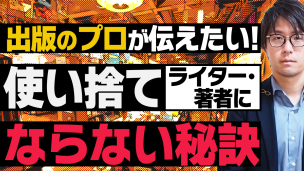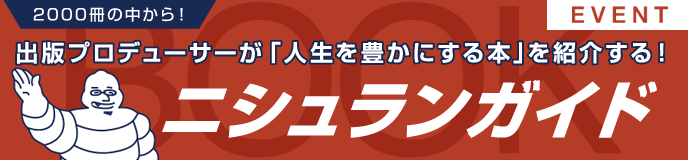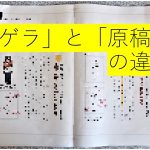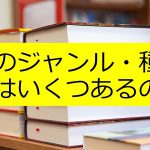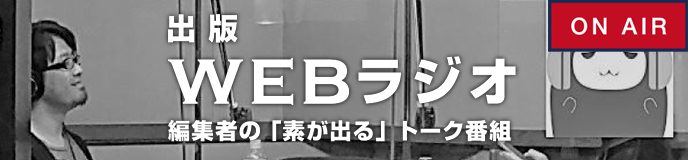「そのパン屋の腕を知りたかったらクリームパンを食べればいい」って言葉が好きな、出版プロデューサー西浦です。
出典元忘れたんですが何かで観たか読んだかしたんですよね。クリームパンは目立たないけど、定番で老若男女を問わないってことでしょうか?
さて、毎日更新72日目。
目次
伝わらない文章の多様性
出版プロデューサーをしていると、「プロではない」人の文章をたくさん読むことになります。
作家さんやプロのライターさんと違って、読みにくい文章や、その人の癖(悪い意味で)がそのまま残った迷文に悩まされる日々です。
かくいう僕も自覚してるだけで、たくさんの悪い癖があります。「ということ」を多用しがちとか(苦笑)
これら読みにくい文章も、たくさん見ていくうちにタイプがあるように思えてきました。
- リズムが悪い文章
- 同じ表現が続く、飽きる文章
- ありきたりでオリジナリティのない文章
- 余計な言葉が多い回りくどい文章(僕、このタイプ)
- 専門用語だらけの文章
- 感情乗せすぎの文章
などなど…ほかにもいろいろ出てきそうです。
そんな中で今回は「読む気を奪う文章」と、その原因と対策について考えてみます。
読む気を奪う文章
「読む気を奪う文章」というのは、読んでいて「これ以上読めない…」って、思わず読むのを諦めさせる文章です。それはひどいことが書いていて胸がムカムカするということではなく、読んでいると脳内に「?」マークがどんどん増えてきて、先に進めるのを脳が拒否します。
このタイプの文章を何度も読むうちに、なぜ読む気が失せるのか、分かってきました。
実は「接続語」の使い方が下手なのです。
接続語というのは、簡単に言えば「文章と文章をつなぐ言葉」のことです。文章と文章の関係を読者に伝える機能があります。
例えば、
- 「だから」とか「なので」などの順接
- 「しかし」「ところが」などの逆説
- 「また」「かつ」などの並列
- 「さらに」「そのうえ」などの添加
- 「なぜなら」「つまり」などの説明
- 「または」「あるいは」などの選択
- 「例えば」「いわば」などの例示
- 「ところで」「さて」などの転換
などたくさんの接続語があります。辞書などによっても分け方は違うようなので、あくまでざっくりの理解でOKです。
この原稿の最初の方で使った「さて、毎日更新72日目」の「さて」は「転換」で、読者の脳に「話が変わりますよ」「ここから新しい話題ですよ」と伝えています。
また、接続語を紹介するのに使用した「例えば」は、『これから、例を紹介しますよ』と読者にメッセージを発しているというわけです。
接続語とクリームパン
「そんなこと、わざわざ言われなくても知ってるよ?」と思われたでしょうが、それこそが接続語のすごさ、重要性の証明です。
たくさん存在する接続語について、僕らは「なんとなく」で意味や雰囲気を理解しています。
ゆえに、そればかりか、のみならず、なお、もっとも、やがて、むしろ、かえって・・・など全部、なんとなく理解できますよね。
この接続語がガイドになって、今読んでいる文章と先ほどまで読んでいた文章との関係を理解できるのです。
目立たないけれど、定番で、じつはすごく重要な機能を果たしているという意味で、文章術における「クリームパン」のような存在が接続語なのです。
接続語を見ればその人の文章力がわかる・・・かも。
ではこの接続語の使い方を間違えていたり、ほとんど使えていなかったらどうなるでしょう?
例えば「つまり」や「なぜなら」で始まった文章なのに「~からです」という説明が出てこない。
すると『ん?結局どういうこと?』『説明はどこにあるの?』と、はてなマークを浮かべながら次へ、次へと文章を読み進め、説明を見つけられないまま「さて」などの接続語で次の話題に移っていきます。
これは相当ストレスでして、日ごろから本や文章を目にする人ほど、惑わされます。
文章は必ず上手くなる
小説家やポエマーでないので、一般書の著者は名文家である必要はありません。
しかし、とりあえずは「読もうと思えるレベル」の文章にしないと編集者さんに直してもらうことさえできません。
読みにくい文章を「読める文章」にさえすれば、そこから先は編集さんが伝わる文章までもっていってくれます。
そのためにも「自分の文章は、なぜ読みにくいのだろう?」と思う方は一度、接続語を見直してみると良いでしょう。
(もちろん、実際には読める文章だけではダメで「刺さる」言葉、などのオリジナル要素が必要です。ただ文章力という意味では読めるレベルでOK)
しかし、今、接続語を上手に使えていなくても気落ちしないでくださいね。
「書けている」だけでまずは十分すごいのです!意識して書けば、文章は必ずうまくなりますので!