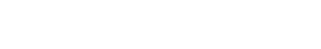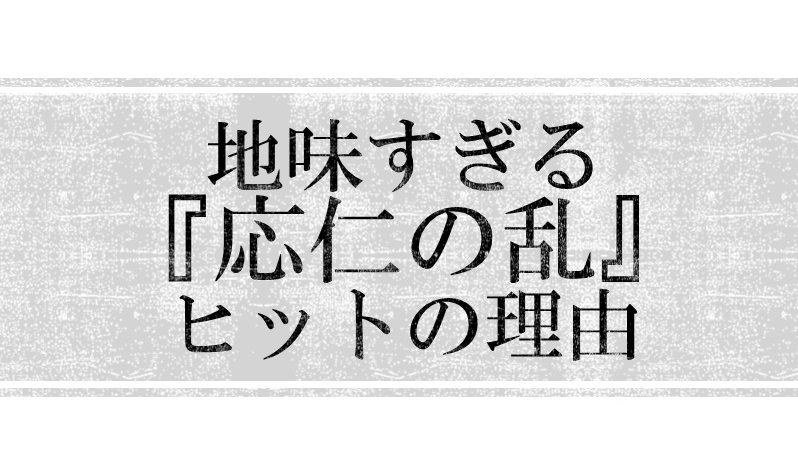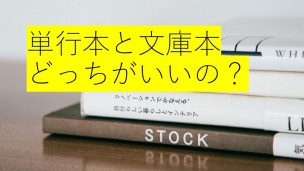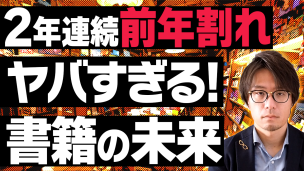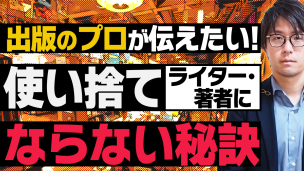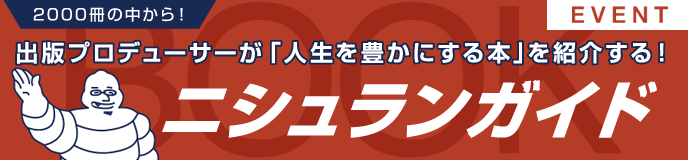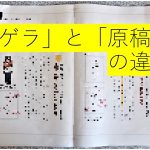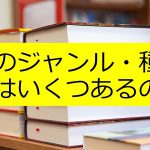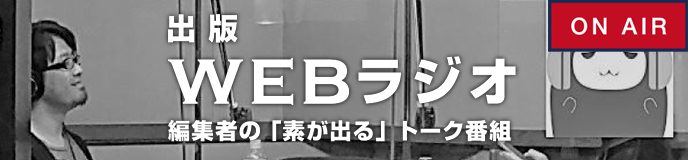「トーストにはチーズをのせるだけでいい」で有名な出版プロデューサー西浦です。でも「小倉あんトースト」ってもう何してくれてんの!?っていうくらい美味しいですよね。
毎日更新68日目。
今週の出版用語解説は『図解版をムックで出しませんか?』という言葉についてです。
目次
図解版をムックで出しませんか?の真意
「図解版をムックで出しませんか?」とは…
売れた著者に対し、編集者より提案される次回作のお誘い。でもあんまり企画を練った形跡はない。
ベースになる本とは別の出版社からも誘われることがある。このケースは危険な香りだ。
背景
出版業界はかなりデータ至上主義であり、その結果「実績至上主義」に陥っている出版社、編集者も多い。
ベストセラーの第二弾は、その意味で安牌であり、第二弾の企画が当然進行しやすい。
これは著者本人としてはありがたく、第二弾は前作の実績があるので初刷部数も大きく、元の本との併売も狙えるので願ったりかなったりだ。
ただ、1冊目の実績があるぶん失敗しにくいが、逆に1冊目を超えることもほぼ100%ないというデメリットもある。
感覚的には1冊目の25%~30%くらい売れればいい方かなと思われる。
第二弾を出す真の目的はそれ自体の売上もさることながら、併売による「1冊目のさらなる売り伸ばし」にある。
以上2つの
- 実績がある本の第二弾は売りやすい
- 第一弾のさらなる売り伸ばしが目的
という背景から第二弾の企画はけっこう思考停止のパターン化がされていて、その代表選手が「実践編」と「図解版」である。
概要
さて第二弾の企画「実践編」と「図解版」であるが、特に図解版はノーアイデアに近い。
なぜなら本当に図解が有効な企画なら、最初から図解多めで作ってるはずだからだ。
しかし他社からしたら売れてる企画さえ持って来られればよく、愛着もないため「スピード重視」で焼き増し企画を提案される。
その結果「売れた本の第二弾が決まる前に、うちで取れるもんならとろう!」とばかりに他社の編集者から「図解版をムックで出しませんか?」という誘いが来るのだ。
この誘いは1冊目を一緒に作って、売り伸ばしてくれた出版社に対する不義理になるので丁重にお断りするのが99%正解だと思われる。
よっぽど1冊目の出版社や編集者を信用できない状況なら別だろうが。
なので基本的には他社からのお誘いは「お誘いが来るくらい売れてるんだ~♪やったね!」と思っていれば良い。
同じような意味でいわゆる「パクり」企画も、内心面白くないだろうが笑っていれば良いと思う。それぐらい注目されたということだから。
対策
さて第二弾企画について話を戻す。
第二弾企画で「売れるもの」をつくるのはすごく難しい。なぜなら1冊目を作るために、ベストなアイデアを出してしまっているからだ。この状態でさらに面白い企画を考えるのは、組み立てたプラモデルに入っていた予備の部品だけで、新しいプラモデルを作るようなものだ。もう1つ新しい企画を作れるくらいコンテンツの種類が豊富な著者は稀なのだ。
もう一つ付け加えるならば、「どうしても1冊目に発想が引っ張られがち」という難しさもある。シリーズ化を考えた時に、核となる部分を変えるわけにもいかず、発想の自由度が落ちてしまうのである。
その結果「前作とだいたい同じことを書いてある」企画や「実践編」「図解版」になってしまいがちだ。
これに対する打開策はないのだろうか?
ヒントは稀にいる「ブームが去った著者を、再ヒットさせる他社の編集者」の存在にある。
彼らはすでに確立した著者のノウハウやコンテンツを、全く違う視点や読者に置き換えることで、ベストセラーにしてしまうのだ。
彼らは「他社の人間である」「かつてのブームから時間が経っている」という点で、通常の第二弾企画とはある程度自由な環境で発想できる。
「元の本の企画に引っ張られにくい」ポジションにあるというのが最大の違いなのだ。つまり1冊目に捕らわれずにうまく「ハズす」ことが「新しさ」を生む秘訣である。
というわけで、あなたが「売れる第二弾」を出したければ、1冊目と同じ出版社でも担当編集者とは別の編集者(後輩とか他部署とか)にミーティングに加わってもらうとか、なるべく視点を変える努力が有効かもしれない。
チーズトーストが美味い、至高!と信じてやまない人間には「小倉あんってトーストに合うよね」という発想が必要なのだ。「次は何チーズをのせようか?」「チーズを何にかけようか?」とチーズに囚われてしまっては良い企画は生まれない。
自分の本を他者の本のように見る視点が必要なのだ。