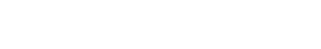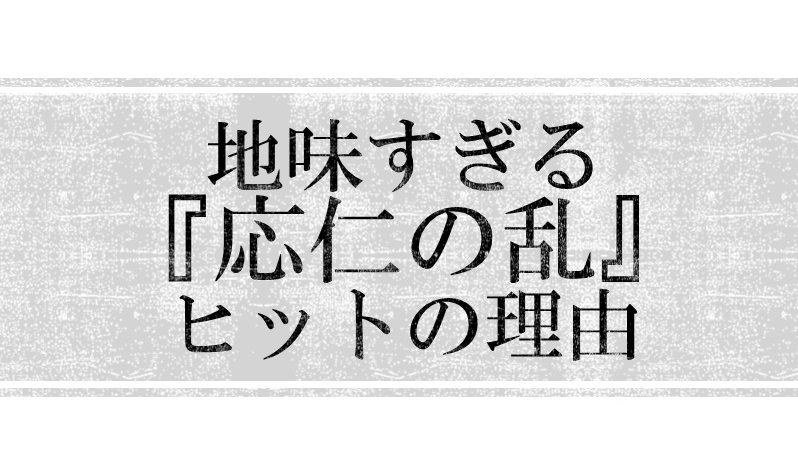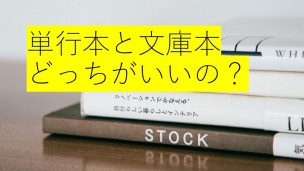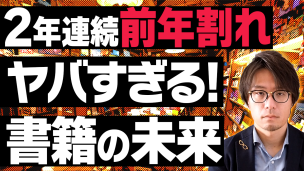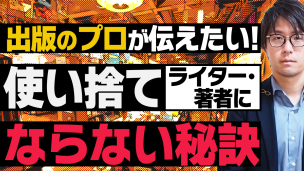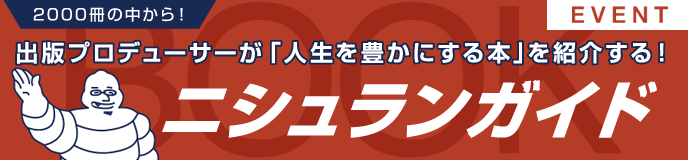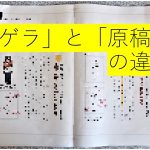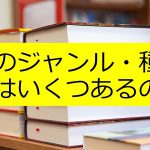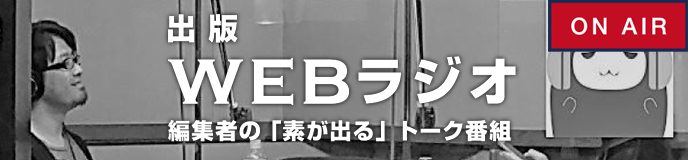出版プロデューサーの西浦です。
実はプロデューサー以外に「マスコミ就活支援」の仕事もしていまして、
先日、とある大学のキャリアセンターさんと打ち合わせをしていたんですけど、
その席でこんな話を聞いたんですね。
「事務職希望なので、編集者に興味あります。」
という学生がいるとのことです。(実話)
いやー、打ち合わせ中にみんなで笑った笑った。
・・・全国の編集者の皆さん、
事務職だと思われてますよ(笑)
(あ、怒らないで!石を投げないでくださーい!そんな分厚い〇〇誌投げられたら骨折します!)
西浦 「え、編集事務っていう仕事もありますけど。。。そういう意味ではないんですよね?」
キャリアセンターの方 「はい。編集=デスクワーク=事務という理解です」
・・・(´・ω・`)
もちろん、そういう学生ばかりというわけではなく、「そういう子も一部いる」という話です。
そういう一部の学生に関しては「研究不足」という話で解決しますし、
単純に仕事というもののイメージがついていないんだと思います。
ここまでなら、ちょっとした笑い話。
出版社の皆さんとの忘年会で話せば、さぞやウケるだろうなぁと思っていました。
でも、ふと思ったんです。
「いや、これは笑い話じゃないんじゃないか。怖い話なんじゃないか?」と。
学生が研究不足ということは、逆に言えばこっちの告知不足かもしれないし、もっと言うと「魅力不足」なのです。
出版業界側に、「知りたい」「何が何でもこの仕事に就きたい」と思わせる魅力が足りなくなってきてるんだなと感じさせられました。
目次
僕らが作ってしまった現状
出版業界は今の学生にとって、かつてほど魅力のある業界ではなくなっています。
これはもう、悲しいかな現実ですね。
売上は落ち続け、出版社も書店もどんどん消えていってる。
みなし残業、労働裁量制などの導入で、年収も落ちてきた(一部を除いて)
言うまでもなく、時間的、体力的、精神的にハードワークです。
学生も、このことを何となくは知っているので
「出版て斜陽産業なんですよね?」と、就活相談をしていて聞かれることが増えてきました。
若い彼らにすれば、自分が引退するまで稼げる業界に行きたいと思うのは人情でしょう。
それでもこの業界を目指そうという意志ある学生が受けてくれるわけですが、
やはり10年前と比べてものすごく受験者数が落ちています。
最近だと講談社でES提出3,000名前後です。
私が受験したころと比較すると1,000人単位で減ってますね・・・。
また、内定辞退ってあるじゃないですか。
昔は、出版社の内定辞退した人は、より志望度の高い別の出版社に入社してました。
そうでなくとも、電通とかNHKとか他のマスコミ企業に行ってました。
ですが今はまったく他業界に移籍されることがあると聞きます。
受験者数が担保していたもの
出版の世界って、原材料=人みたいな部分があるじゃないですか。
厳密には紙とインクが原材料ですが、
実際のところは企画力とかセンスだったり、経験・知識が原材料だと思うのです。
クリエイティビティが人のセンスに依存しているということは、
面白い人からは面白い本ができるし、
つまらない人からはつまらない本しかできない
ということです。
この業界に「面白い人」がどんどん来てくれないと、面白い本が、企画が生まれなくなってしまいます。
質を量が担保するところはやはりあって、
倍率数百倍の試験を通過してきた「変わり者」が出版業界に集まっていたから
ある程度、「面白い人」のクオリティが保たれていたと思うのですが、
それがちょっとずつ下がってしまうのは、けっこう怖いです。
このままだと
斜陽産業で人気減少→受験者減少→
人の質劣化→作品の劣化→さらに売れない
→斜陽加速→さらに人気減少・・・
ていう負のスパイラルに陥ってしまうのでは・・・
もちろん、興味本位の受験者の増減と内定者の質に純粋な比例関係があるとは思いません。
本当にできる学生は、まわり関係なくできるヤツになりますから、環境を自分で変えていくので。
ただ、母集団の規模が小さくなると、中での競争も緩くなり、磨かれる機会は減るだろうな・・・と。
あんまり悲観的な話はしたくないのですが、やはり心配です。
この業界に食わせてもらってる身としては、対岸の火事では済まないからです。
未来のために個人個人にできること
もちろん出版社側も学生へのPR活動をしています。
しかし某出版社人事が言うには大学へ「説明会行きますよー」と申し込んでも、就職に強い大学にはスルーされるそうです。
しかもかなり有名な出版社です、知名度も圧倒的にある。
それでもそういう扱いなのかと驚きました。
説明会の枠の取り合いですでに負けてる・・・
このままだとどんどん負のスパイラルに陥ります。
そうならないために、出版業界の方々にお願いしたいことがございます。
- どんどん面白い本をつくってください。
買って読んだ本がつまらなければ、「損した」と思い、読書離れしていくのも道理です。
読んだ人が「面白かった!」「感動した!」と思えばまた他の本も買ってくれるし、
そういう体験が増えれば「本を作る仕事がしたい」「本を売る仕事がしたい」という学生が増えるでしょう。
みんなそうだったでしょう?
- どんどん売れる本を作って稼いでください。
売れる本が出来れば業界全部が潤う。簡単なことじゃないですが、一人一人が平均部数伸ばしていきましょう。増刷率上げて行きましょう。営業の皆さんガツンと「力」見せつけたりましょう。
増収増益を続けている出版社もちゃんとあります。
業界全体の景気を一部のコンテンツ頼みにするのではなく、底上げしましょう。
斜陽じゃなくなれば未来に希望を感じ、学生も増えますよね。
- どんどん大人に、自分の仕事の面白さを話してください。
「就職に関する意思決定において、誰の影響を受けたか?」という質問に「母」と答える女子学生が多いそうです。
最近では男子学生でも「母」と答えるとのこと。一人一人の学生にとって、やはり「親」は最も身近な仕事との窓口です。
自分の子供はもちろんですが、よその子の親ともどんどん話をして「この仕事がどれだけ楽しいか」「素晴らしいか」など楽しくお話ししてください。(自慢はダメですよ)
身近な大人から話を聞くことで、学生の耳にこの業界の魅力が伝わります。
「置けば売れる時代は終わった」というのは周知の事実ですが、
すでに「出版人気の時代」も終わりつつあると感じます。
出版プロデューサーというのはこの業界の末席の、小さな存在だと思ってますが、
それでも出版が生き残る道を見つけてやりたいと思って独立しましたし、
だから「出版プロデューサーは業界のビフィズス菌になれ!」なんて言ってます。
というわけで今回は「それが難しいんだよ!」って言われるかもしれませんが、
出版業界と一緒に心中しないために、ビフィズス目線のお願いでした。
出版業界の皆様、よろしくお願いいたします!